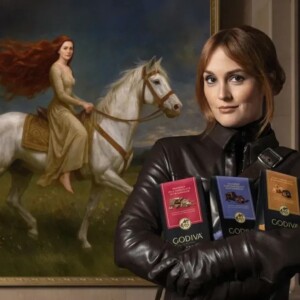ペプシコ、25年ぶりのコーポレート・アイデンティティ刷新─期待と失望のはざまで
ペプシコはゲータレード、クエーカー、シエテ、そしてペプシなど500以上のブランドを傘下に抱える企業である。コーポレート・ロゴは約25年間にわたり地球儀風の円と大文字の「PepsiCo」で親しまれてきたが、今回、同社はコーポレート・アイデンティティを一新し、小文字に移行した新ロゴを発表した。パンチラインは「Food. Drinks. Smiles.(食品。飲料。笑顔。)」である。

新ロゴの構成と狙い
新しいロゴは小文字の「pepsico」を基調とし、特に「p」の周囲に配されたシンボル群が視覚的な焦点となっている。シンボルは複数の形状で構成され、それぞれが企業の価値や事業領域を表すことが意図されているという説明だ。具体的には、農産由来の原材料を示す穀物や食品を想起させる形、飲料や水分補給を表す青い流線、環境や「pep+で勝つ」を示すという緑の葉状の要素、そして「私たちの未来を導く価値観」を象徴する枠組み──といった説明が付されている。さらに、濃い緑色で表現された「笑顔」を示すマークが消費者中心主義を示す要素として添えられている。
ペプシコは新しいカラーパレットについて「食品を育む豊かな土壌、爽やかな飲料、そして人と地球へのコミットメント」を反映した鮮やかな色合いだと説明している。新タグラインは、食品と飲料という事業の両輪と、それがもたらすポジティブな体験を短く表現したものだ。
複雑さと伝達性のジレンマ
今回のリニューアルに対する第一印象は賛否が分かれるだろう。新ロゴは多層の象徴性を狙っている一方で、視覚的にはやや複雑で説明的に過ぎる印象を受ける。ロゴ自体が何を意味するのかを理解するために解説が必要であれば、それは「識別子」としてのロゴの本来の機能を満たしているかを再考する余地がある。
企業ロゴは通常、瞬時に「それが何であるか」を伝えるべきである。だが今回のマークは多数の要素を内包しており、消費者が棚や画面で即座に認識・連想できるかは疑問が残る。色味についても、ペプシコ側の説明とは裏腹に「鮮烈さ」や「記憶に残る強さ」が不足していると感じる人は少なくないだろう。
また、スマイルや葉などの親しみやすいモチーフをコーポレート・マークに取り入れること自体はあり得る手法だが、既に似た表象を用いるグローバルブランドが存在する点を踏まえると、独自性の確保という観点での挑戦も伴う。

ブランド認知の課題と戦略的示唆
調査によれば、消費者のうちペプシ以外のペプシコ傘下ブランドを挙げられる割合は依然として低く、同社の持つブランド群全体の認知向上が課題であるとされる(引用元に基づく統計を参照)。コーポレート名やロゴの刷新は、企業の多様な事業を「ひとつの物語」として再提示する好機であるが、同時に「何を変えたのか」「何が変わらないのか」を消費者にわかりやすく伝えるコミュニケーション設計が不可欠である。
もし目的が「ペプシコという企業がペプシとは別に何をしているのか」を消費者に広く認知させることであるなら、ロゴ単体の刷新だけでなく、各ブランドとコーポレートの関係性を示す実証的な施策や、段階的な浸透計画が求められる。
展開計画と導入チャネル
新ブランドは公式サイト(PepsiCo.com)ならびにペプシコのグローバル・ソーシャルチャネル(LinkedIn、Instagram、TikTok、YouTube)で公開され、今後、各市場やタッチポイントに応じて段階的に導入されていく予定である。市場ごとの導入タイミングや、パッケージ、店頭、広告といった具体的接点での適用方法が、ブランドの受容性を左右するだろう。
新しいコーポレート・アイデンティティは、ペプシコが多角的な事業とサステナビリティ志向をブランド化したいという戦略的意思を反映している。しかし、その表現はやや説明的かつ複雑であり、即時的な識別性や強い視覚的印象を残す点では課題を抱えているように見える。ブランドは時に「分かりやすさ」と「豊かな意味性」の両立を迫られるが、今回の刷新はそのバランスの取り方に疑問符を投げかけるものである。
今後、ペプシコが新ロゴを通じてどのように消費者との関係を再構築し、傘下の多彩なブランドの認知を高めていくのかが注目される。(出典・画像:PEPSICO、CREATIVE BLOQ )