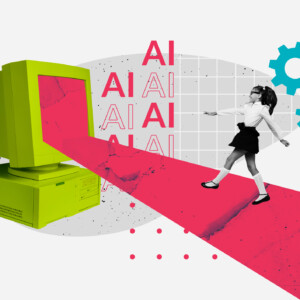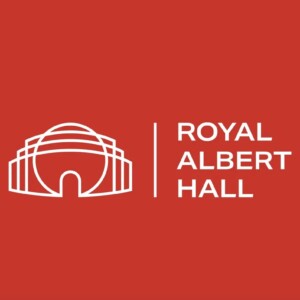ユニリーバがスポーツ・マーケティングを放送の枠を超えて進化させる
スポーツが“最後のモノカルチャー”として持つ力
ユニリーバは、スポーツをもはや“テレビ中継の広告枠”だけの場とは見ていない。全米オープンでの「脇の下大使」企画から、マヨネーズの香りがするフレグランスといった遊び心あふれる施策まで、スポーツを多様なアクティベーションが試せる実験場として位置づけている。
メディア環境が細分化し、視聴者の関心が無数のプラットフォームへ拡散しているなかで、スポーツは依然として“共通の話題”を生み出せる数少ない領域である。コードカットが進んでも、スーパーボウルのようなイベントはリニアテレビで圧倒的な視聴率と幅広い層のオーディエンスを引き寄せ続けている。
しかし、そのスポーツもまた視聴スタイルや関わり方が変化しつつあり、ユニリーバのような巨大CPG企業は、デジタルやソーシャルファーストな消費行動の拡大を踏まえて戦略を調整している。同社の米国におけるスポーツマーケティング投資は、2024年から25年にかけてほぼ倍増しており、2026年に向けてもさらなる拡張が計画されている。
ソーシャル・ファーストで仕掛ける“多対多”のスポーツ活用
Dove Men+Careは、FIFAワールドカップ26のスポンサーシップを足がかりに、新たなファンコミュニケーションを試みている。元NFL選手マーショーン・リンチと、米サッカー界の若きスター、トリニティ・ロッドマンが共演するキャンペーンでは、「スーパーファン合宿」という設定を通じて、アメリカンフットボール的な“フットボール”と、サッカーとしての“フットボール”の違いをユーモアを交えて描き、北米開催となるワールドカップのチケット懸賞をSNS中心に訴求している。主要な場はMetaとTikTokであり、従来のテレビ中心の露出とは異なるアプローチだ。
ユニリーバ・パーソナルケア・ノースアメリカのチーフ・メディア&マーケティング・ケイパビリティ・オフィサーである横井龍氏は、ワールドカップのようなグローバルイベントを、「一方向の放送」から「多方向の対話」へと転換する象徴的な機会ととらえている。つまり、かつては大規模なテレビ広告で一斉にメッセージを投げかけていたが、今はさまざまな場やレベルでファンとつながる“多対多”のマーケティングを重視しているということだ。
この背景には、親会社のユニリーバが全社的なリストラの最中にあり、価格に敏感な消費者や、新興のD2Cブランドをはじめとする“ディスラプター”との競争にさらされているという事情がある。CEOのフェルナンド・フェルナンデスは2024年3月、広告費の半分をソーシャルメディアに振り向ける方針を示し、インフルエンサーとの協業を20倍に増やすと明言した。こうした方針は、スポーツマーケティングの領域にも色濃く反映されている。
ユニリーバは、スポーツを「多様なコミュニティがそれぞれの角度から関われる場」として捉え、従来型のテレビ広告だけでは拾いきれない共感や会話を、デジタル・ソーシャル軸で設計し直しているのである。
ユニリーバはこれまでも長年にわたりスポーツスポンサーシップを活用してきたが、近年はその存在感をより一段と高めている。スーパーボウルはその代表例であり、Hellmann’sは2021年にスーパーボウルCMデビューを果たした。横井氏はこれを「ステップチェンジ」と表現している。さらにDoveブランドは直近2回のスーパーボウルに登場し、身体への自信や、若い女性のスポーツ参加を支援するメッセージを発信した。
スーパーボウルの30秒枠は700万ドル以上に達することもあり、その投資は非常に高額だが、その裏側にはソーシャルやデジタルを中心とした継続的なアクティベーションが積み上がっている。単発のテレビ露出ではなく、複数チャネルを組み合わせた長期的なブランド・ナラティブの一部として位置付けられているのである。
SNS上で話題になった瞬間を巧みに取り込む事例もある。テネシー・タイタンズのQBウィル・リーヴィスが「コーヒーにマヨネーズを入れて飲む」と語りバイラル化した際、Hellmann’sはすばやく同選手と長期パートナー契約を結び、その奇妙な飲み方を軸にした模擬記者会見動画や、「マヨネーズ香水」というネタ系フレグランス、疑似ラグジュアリーブランド風キャンペーンなど、ユーモアと商品特性を掛け合わせたコンテンツ群を展開した。
Doveは、2025年の全米オープンのスポンサーシップに合わせて、「脇の下大使」と呼ばれる参加者を募集するTikTok企画を立ち上げ、制汗剤を自然な形で訴求した。テニストーナメントの会場周辺でUGC(ユーザー生成コンテンツ)を生み出し、「汗とニオイが気になる場所に清潔さを届ける」というテーマを、コミコンや音楽フェスなど他の“汗だくイベント”にも拡張していく構想と連動させている。
横井氏によれば、ユニリーバは「すべてのバイラル現象に飛びつく」わけではなく、自社が“ブランドバース”と呼ぶ枠組み、すなわち、そのブランドならではの価値や特徴を増幅できるストーリーかどうかを軸に判断しているという。加えて、ソーシャル上の施策をリアルなイベントや体験型マーケティングへとつなげられるかどうかも重要な視点とされている。彼は「ソーシャルとリアルな瞬間を掛け合わせることで、“多対多”のコミュニケーションを一気に加速できる」と述べている。
“Culture to Cart”:文化から購買へつなぐストリーミングと小売メディア
ユニリーバが「culture to cart」と呼ぶ考え方は、カルチャー上の存在感と実際の購買行動をいかに近づけるかという発想に基づく。その意味で、スポーツのストリーミング化は重要なインフラとなりつつある。同社はAmazonと早い段階から協業し、Doveなどのブランドが地理・属性・行動データに基づいて最適な世帯に広告を届けるオーディエンスベースのクリエイティブツールを活用してきた。
Amazonが持つNFL「Thursday Night Football」やNBAレギュラーシーズンなどのプレミアムスポーツコンテンツと、小売メディアネットワークを組み合わせる力は、同社の広告ビジネス拡大の原動力になっている。このモデルは、ウォルマートによるVizio買収などを通じて、小売業界全体にも広がりつつある。
横井氏は「ストリーミングの発展によって、従来はリニアテレビの枠内でしかできなかったことが、よりデジタル的な精度を持って実現できるようになりつつある」と指摘する。
目的と成果の両立:ユニリーバが守り続ける“ブランドの上流”
一方でユニリーバは、パフォーマンス・マーケティングを重視しながらも、ファネルの“上”であるブランド構築や目的訴求を手放してはいない。今年のスーパーボウルにおいてDoveは、「身体への自信を失ったことでスポーツをやめてしまう少女がどれほど多いか」という課題にフォーカスしたCMを放映した。これはDoveが長年取り組んできたテーマであり、感情的なインパクトと同時に、少年・少女スポーツのコーチを務める父親層など新たなオーディエンスにも届いたとされる。
横井氏は、「スーパーボウルのような場では、短期的な売上へのインパクトと、長期的なブランド構築の両方を見据える必要がある」と語る。そして、「こうした大型イベントを起点に大量のマーチャンダイジング機会が生まれるため、小売パートナーにとっても“売り切れる”ことが非常に重要だ」と指摘する。
ユニリーバのスポーツマーケティングは、放送枠の買い付けから、カルチャー・ソーシャル・リテールをまたぐ複合的なエコシステムづくりへと明確にシフトしている。スポーツという巨大な舞台で、ブランドは「見られる」だけでなく、「語られ、体験され、最後にはカートに入る」存在へと設計されているのである。(出典:Unilever, Marketing Dive)