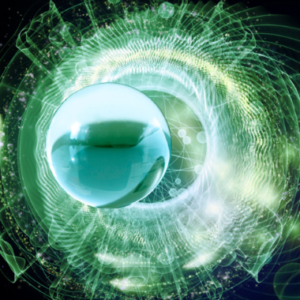パタゴニア、「正直なブランド」への揺るぎない信頼と違和感
「パタゴニアなら間違いない」—サステナブルな文脈において、このブランドほど強固な信頼を獲得している企業は稀である。「地球を救うためにビジネスを行う」というミッション、あえて消費を抑制する姿勢を打ち出した象徴的な広告、さらには創業者が株式を環境保護目的に譲渡した決断まで、同社は一貫して倫理的企業像を体現してきた。
そうした背景のもと、2025年に公開された全154ページの報告書『Work in Progress Report 2025』は大きな注目を集めた。サプライチェーンに内在する構造的問題や、理想とは程遠い環境負荷の実態を、定量データと具体的なエピソードの両面から詳細に開示した内容だったからだ。企業の不都合な現実をここまで包み隠さず示す例は少なく、「ここまで正直な開示は前例がない」と高く評価されたのも無理はない。
しかし、その称賛の渦中で、静かに浮上した問いがある。それは「正直であることは称賛に値するが、それだけで十分なのか」という疑問である。
正直さは免罪符になり得るのか—パラドックスの収益化
パタゴニア自身も、自らが抱える矛盾を自覚している。報告書では、社会的・環境的責任を掲げながらも、製品を生産する行為自体が地球の有限な資源を消費しているという根本的な緊張関係が率直に語られている。完璧な企業像を装うのではなく、矛盾を前提に現実主義的な改善を重ねていく姿勢は、確かに評価されるべき出発点だ。
一方で、デンマークの建築家であり活動家でもあるキャスパー・ベンジャミン・ライマー・ビョルクスコーフ氏は、この「正直さ」そのものに潜む危うさを指摘した。彼の問題提起は、「正直な開示が、現状を温存するための装置になっていないか」という点にある。
企業が自らの不完全さを認めることで、消費者は「このブランドは誠実だ」という安心感を得る。その結果、「ここで買うことは倫理的に正しい」という感覚が生まれ、過剰消費への罪悪感が相対的に薄れてしまう。ビョルクスコーフ氏は、これをパラドックスの解消ではなく「パラドックスのマネタイズ」と表現する。すなわち、消費行動を通じて環境問題から脱却できるかのような幻想を補強し、エコロジカル・オーバーシュートという根源的な問題から目を逸らす機能を果たしてしまうのではないか、という指摘である。
効率化の先にある「十分性」という未踏の領域
この議論の核心にあるのは、「環境効率」と「十分性」の違いである。多くの企業が取り組むのは、リサイクル素材の採用や省エネルギー化など、製品一単位あたりの環境負荷を下げる効率化の施策だ。これは確かに「より良い」取り組みではある。
しかし、事業が成長し、生産・販売数量そのものが拡大し続ければ、総量としての環境負荷は増え得る。仮に一製品あたりの負荷が半減しても、販売数が三倍になれば、地球への総合的なインパクトはむしろ大きくなる。「少しマシな製品」を大量に生産することは、根本的解決ではなく、問題の先送りに過ぎない。
一部の専門家が「生産総量を減らさない限り、真のサステナビリティには到達しない」と厳しく指摘するのは、特定企業を攻撃するためではない。むしろ、パタゴニアほどの理念を掲げる企業でさえ、成長という前提から完全に自由になれない現実を通じて、資本主義システムそのものの限界が露わになっているからだ。
もっとも、透明性を示した企業を過度に批判すれば、企業が沈黙を選ぶ「グリーンハッシング」を招く危険もある。だからこそ、正直な開示は評価されるべきであり、その情報公開があって初めて、ここまで踏み込んだ議論が可能になる。
重要なのは、その先である。情報を開示しているから良い、リサイクル素材を使っているから十分、という地点で思考を止めてはならない。修理や再流通による製品寿命の最大化、新規生産から維持管理へのビジネスモデル転換など、「総量を減らす」方向に踏み込まなければ、サステナビリティは成長を正当化する言葉に堕してしまう。
パタゴニアの報告書が突きつけた本当の問いは、「どのブランドを選ぶべきか」ではない。「それは本当に必要なのか」という、より根源的で不都合な問いである。私たちは今、サステナビリティをもう一段深いレベルで再定義する局面に差し掛かっているのかもしれない。(出典・画像:パタゴニア)