
自然資本を核にした事業戦略とは―循環型ビジネスの未来
小西圭介
自然資本を前提に経済を再設計する「第二の近代」
20世紀型の経済は、成長を至上命題とし、資源の大量消費と拡大再生産を軸に動いてきた。その背景にあるのは、自然を“無償の供給源”とみなす思想であり、自然という資本を外部性として無視する経済設計であった。しかし、気候変動、生物多様性の損失、水資源の枯渇といった環境危機が進行する中で、このモデルは古びてもはや限界を迎えつつある。いま企業と社会は、この自然資本の回復を前提に経済を再設計する「第二の近代」に突入している。
自然資本とは、土壌、水、森林、大気、生態系など、人間社会と経済活動が依存するあらゆる自然の構成要素を指す。当たり前のことだが、この資本が損なわれれば、農業、漁業、観光業はもちろん、製造業や都市生活も成立しない。自然資本は単なる“環境”ではなく、経済そのものの前提であり、それ以上に人間も自然の一部であり、人が地球で生きていく上で代替のきかない存在である。これを「守り、再生し、生かす」ことが、今後のビジネスや社会活動にとっても中核課題となる。
たとえば気候温暖化は、われわれの住む陸上より海洋でより深刻化している。地球の2/3を占める海で育つシーフォレストと言われる大型藻類は、地上の森林に匹敵するCO2吸収を果たしている重要な自然資本だ。さらに葉や木が分解されて炭素が大気中に戻る森林と違って、海中林ではCO2を溶存有機炭素として深海まで運び、地層に数百〜千年も蓄積されて温室効果を減少できる。
ところが海水温上昇が加速するこの10年で、そのCO2吸収源である藻場が大きく消失している。水温上昇によるエルニーニョ現象の発生で海藻への栄養分の供給が減ったこと、うにの代謝が上がって、海藻を食い尽くす磯焼けが大量に起きていることなどが原因だ。世界最大の藻場であるオーストラリア海域では、タスマニアでこの50年でジャイアントケルプの9割以上が消失するなど、温暖化をさらに加速させるとともに、藻場が生息・産卵場所となっている魚介類も減少してしまっている1。

ジャイアント・ケルプの森は重要なCO2吸収源であり、魚介類の生息・産卵場所として機能している
あるいは、「土」は5億年前に地衣類とコケが岩石を風化させ、遺骸と粘土を混ぜ合わせて誕生した、有機物として植物を育むのに欠かせない“地球だけの自然資本”だ。ところが20世紀以降の近代農業は、人工窒素を自然界の自然陸上固定量より遥かに大量に投入し、地球上の農地の3割以上が劣化するほど富栄養化と土壌劣化を加速させた。
その結果、わずか27年間で昆虫の76%が姿を消し、植物の受粉を担うハチが絶滅すれば人類は4年で生存できなくなると言われるほど、未来の食料供給は危機的制約に直面している2。土がなければ植物は育たず、循環は断たれ、AI もテクノロジーも無意味になる。綺麗事ではなく、自然の循環を回復することが、これからの経済と文明の大前提である。
循環から再生へ:「再生型資本主義」の台頭
では、自然資本を核とする事業と資本主義的成長は、本当に両立するのか。答えは「条件付きで、Yes」である。成長の定義を「量的拡大」に置き続ける限り、自然の限界と衝突する。しかし、成長の軸を「質的進化」「価値の多層化」「再生能力の増大」に置き換えることで、自然と経済の矛盾は解け始める。
自然資本を利用する限り再生が前提となる。すなわち搾取型資本主義ではなく、自然再生関与型・共創型の経済構造に転換していく。再生によって自然資本の供給能力を高め、それを再び収益につなげるループが可能になるとき、そこに真の意味での「持続可能な成長」が生まれる。循環型経済(Circular Economy)は、資源の浪費を抑え、再利用やリサイクルによって環境負荷を下げる概念であるが、循環させるだけでは自然資本の目減りは防げない。近年はさらに一歩進んだ再生型資本主義(Regenerative Capitalism)が焦点になっている。
2015年にアメリカの経済学者ジョン・フラートンが提唱したこの思想は、単に環境負荷を低減させるのではなく、「自然と社会の健全性そのものを回復させる構造をビジネスの本質に据える」ことを求める3。つまり、自然資本へのダメージを減らすだけでなく、回復させることを目的化し、その過程自体が雇用と経済価値を生むという設計である。じっさいに、都市の再緑化、里山の再生、マングローブによる防災、生物多様性回復を起点とした観光振興など、自然を再生しながら新たな市場を生むモデルは世界各地で登場しつつある。
自然資本はコストか資産か:コストセンターからバリューセンターへ
かつて環境配慮は「コスト」だった。ビジネスにおいてCSRやボランティア活動の延長で語られることが多く、収益には結びつかないとされてきた。しかし、ここに根本的な誤認がある。自然資本は、正しく設計されたビジネスモデルにおいては“コスト”ではなく“収益源”に転化し得る。
たとえば、森林資源を保全しつつ活用する地域材供給モデルや、土壌の健全性を高めることで収量と品質を向上させる再生型農業、水循環を回復させる流域経営などは、いずれも自然資本の回復と経済合理性を両立させている。
再生型農業モデルの開発で有名な、米国ロデール研究所の長期圃場試験では、有機・再生農法が慣行農法より平均収量で5~10%高く、干ばつ年には30%上回ることを示した。土壌の炭素含有量が1%増えれば、1ヘクタール当たり210トンの水保持力が向上する。つまり再生は収量・レジリエンス・炭素クレジットという三重の収益流を生む。4

有機農法研究で世界的に知られる米国ロデール研究所(Rodale Institute)
森林でも同様だ。フィンランドのマテリアル・ソリューション・カンパニーであるUPMの「フォレスト・バランス経営」は伐採と植林を数理モデルで最適化し、生態系サービスを貨幣換算してバランスシートに計上。結果、森林資産価値は5年で約14%増大し、同社株価のリスクプレミアムは欧州同業平均を下回った5。自然資本は確かにキャッシュフローを生む“可変資産”である。

フィンランドのUPMは、ビジネスと森の生物多様性のバランスをとるフィンランド・モデルに挑戦
近年、自然資本の重要性はESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点から注目されてきた。電子機器やエネルギー関連製品にはレアメタル(希少金属)が必須で、製薬業界は生物由来の原料に依存し、鉱業は土地や水の使用によって自然を大きく変質させる。これらはもはや「外部性」ではなく、企業の財務リスクそのものである。自然資本の状態が事業継続性に直結するとの認識が広がれば、企業は“環境保護”の次元を超えて、「事業の持続可能性を測る指標」として自然を捉えるようになる。
ここにあるのは「保全の対価」ではなく、「自然と共に価値を生む経済設計」である。環境が単なる「外部リスク」ではなく、「内部資産」に転化し始めている証左である。
いっぽうで、自然資本が抱える本質的リスクを考えてみると、〈測れない・帳簿に載らない・誰のものでもない〉という“三重の盲点”に凝縮される。土壌微生物や地下水の働きは数値化が難しく、損なわれても企業は負債計上しない。共有林や漁場は権利が曖昧で、守る主体がいないまま劣化が進む。しかも回復には十年単位を要するのに、投資家は四半期で成果を求める。衛星やIoTで監視こそ進むが、小規模生産者にはコストが重く、化石燃料補助という“逆インセンティブ”も残る。危機は家計に直ちに跳ね返らず社会の関心は薄い。
結果として、カーボン・オフセット頼みの帳尻合わせが真の保全を先送りしているのが現実である。いま必要なのは、自然を財務と法の両面で「見える化」し、短期利益の論理を根底から組み替えることだ。
自然資本の資産化:金融の果たす役割と限界
このように自然資本をめぐる動きの中で、グローバルな金融の役割が大きくなっている。ESG投資は広く浸透し、ブラックロックやアリアンツなどの資産運用会社が自然リスクを株価算定に織り込み、ESGファンド残高は世界で40兆ドルに到達した。
こうした資本移動が示すのは、自然資本が〈開示すべきリスク〉を超え〈管理すべき可変資産〉へ格上げされたという事実である。さらに、2023年に正式化されたTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)6は、企業の自然資本への依存や影響を財務上の開示事項とすることで、金融と環境の結節点を構築しつつある。
また欧州では、ネイチャーポジティブな事業に投資する自然資本ファンド(Natural Capital Investment Funds)7が創設され、森林再生、ブルーカーボン(海洋吸収源)、生物多様性回復といった分野への資金流入が加速している。再生型農業の炭素クレジット、グリーンインフラの債券化、生態系修復型PPPなど、金融商品はすでに「自然を稼働資本化する器」として進化を始めている。
重要なのは、自然資本の回復が“非財務的な善行”ではなく、“持続的なキャッシュフローを生む資産”として、金融市場において正統に評価されつつある点である。日本においても地方銀行や地域金融機関がこの文脈で役割を果たし得る。自然と共生する産業群を「地域の資産ポートフォリオ」として捉え、地元の経済循環と金融の論理を接続させることが次なるフロンティアとなる。
しかし、一点ここで誤解してはならないのは、「金融がネイチャーポジティブ経済を動かす主体なのではない」という点である。金融はあくまで“流れを変える力”であり、本質的な価値創造は現場にある。自然資本を実際に再生し、使いこなし、地域社会や顧客と共に新しい価値を築いているのは、あくまで事業創造者なのだ。
例えばパタゴニアは、ソイルフードウェブ(土壌中に存在する多様な生物が、エネルギーと栄養素の流れを通じて階層的・網状につながる”食物網”)を基にした再生型農業スタートアップを支援している。8原料農家の再生型転換費用を前払いし、製品価格に“Regenerative Organic”の物語価値を上乗せすることに成功している。

パタゴニアが支援するリジェネラティブ・オーガニック・コットンを栽培するインドの農場 ©Tim Davis
あるいは2003年に海洋生態学者アラスデア・ハリスらが設立したBlue Venturesは9、アフリカ・アジア・カリブ海などで小規模漁業者と協働し、沿岸コミュニティ主体で漁業を再建し海洋生態系を回復させている。例えばケニア・モザンビークの活動では、沿岸コミュニティが漁獲休漁区を自主設定し、回復した水産資源に付加価値をつけてローカルブランドで輸出している。
Blue Venturesはアフリカで、コミュニティを基盤とした漁業管理とガバナンスによる漁業の生計維持のあり方を再構築
これらの起業家・事業創造者の取り組みに対して、金融はマイクロファイナンスとリスク保証で下支えする役割を果たす。投資の論理は重要だが、それが主役に躍り出てしまうと、本質的な自然との関係性やローカルの実践は空洞化する。自然資本を核とした経済は、現場で再生を行う事業者こそが主体であり、投資はその構造を後押しする装置(重要な装置だが)に過ぎない点は再認識すべきだ。現状は投資に回せる金融資本は沢山あっても、自然資本を再生する事業創造者自体が圧倒的に不足している。
各業界における、再生×価値の実装の最前線
再生型資本主義の転換は農業・林業・漁業などの一次産業の直接的な取り組みだけでなく、あらゆる産業分野で進みつつある、実際に各産業分野の取り組みを見てみよう。
農業分野では、MITの研究を基に創設されたアグリテック企業インディゴAgは、北米と南米で600万エーカー超の耕地を再生型農法へ転換し、土壌炭素を測定して「Agriculture Carbon Credits」を販売する10。農家には1エーカー当たり最大30ドルを前払いし、マイクロソフトやJPモルガンが購入している。三年間で累計200万tのCO₂を土中に隔離し、作物収量も平均5%向上した。
林業・植生分野では、ブラジルの製紙大手スザノ11は自らをバイオエコノミー企業と位置付け、総面積約200万ヘクタールの土地を保有し、その過半を短伐期ユーカリ植林、残りを大西洋岸林やセラード(ブラジル高原に広がるサバンナ)の保護・再生活動に充てることで、原料自給と生態系回復を同時に進めている。AIとリモートセンシングで生物多様性と炭素収支をリアルタイム管理、40万haを大西洋岸林再生コリドーとして連結し、希少種275種を再導入した。森全体のCO₂吸収は年3400万tに達し、BNDES(Brazilian Development Bank)からグリーンボンド10億ドルを調達して事業を拡大中である。
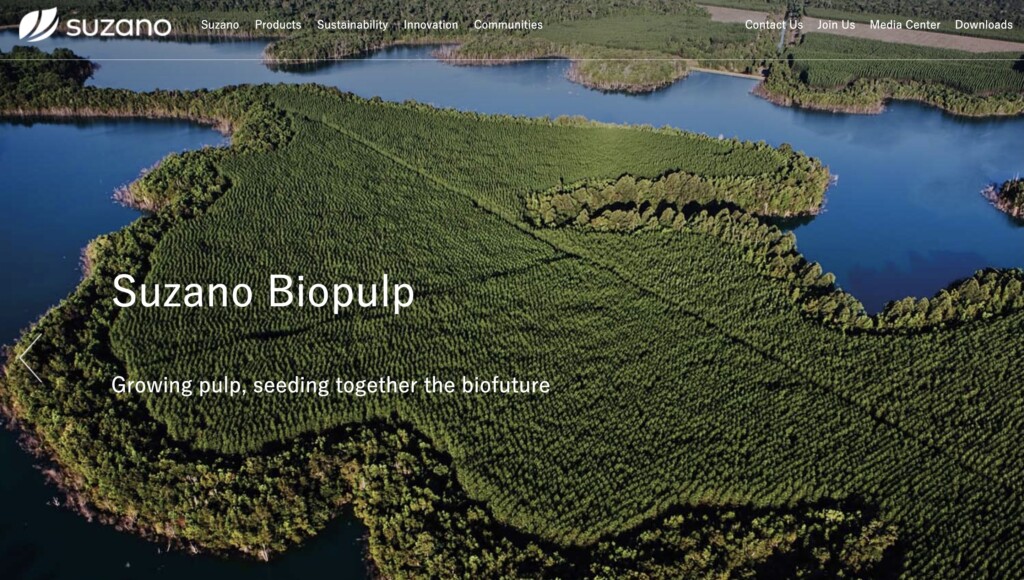
スザノの保有林(同社HPより)
漁業分野では、タイユニオンの「SeaChange ® 360」計画12は、世界38の漁業改善プロジェクトを統合管理し、MSC認証を取得したマグロ・エビを年間70万t供給。収益の1%をマンタ・サメ保護基金に回し、インド洋で5万km²の禁漁区を共同設置した。これにより外部科学調査で対象魚種資源量が平均25%回復した。
エネルギー分野では再生エネルギーへのシフトが進んでいるが、さらに自然資本の再生を組み込んだ事業が進みつつある。たとえばデンマークのØrsted13は洋上風力20 GWを運転・建設中だが、「ネイチャーポジティブ2030」方針で事業海域ごとにサンゴ礁・海草藻場を造成している。英国ホーンシー群では1基当たり0.5haの人工リーフを設置し、三年でタラ稚魚密度が6倍に増加した。社全体で2030年までに純生物多様性正味プラスを達成予定だ。

デンマークの再生可能エネルギー企業、Ørstedの洋上風力発電はネイチャーポジティブ実現を志向する
自動車/交通分野では、電動化やモビリティシェアが主流になりつつあるが、「バイオ・モビリティ」なども試行されつつある。自動車・交通システムでも「壊す」から「再生する」への転換が進む。日本の NCV プロジェクトは車体をセルロースナノファイバーで造り、従来比50%軽量化とLCAマイナスCO₂を実証した14。BMW i Vision Circular は100%再生材と工具不要の“解体前提設計”で資源循環を車内で完結させる。さらに単なるモビリティの提供を超え、都市の緑化や生物多様性に配慮したインフラ整備と連動させることで、単なる移動手段ではない「環境価値を生む交通サービス」への転換が期待できる。
不動産・都市計画分野では、カーボンニュートラル建築や自然共生型のまちづくり(ネイチャーポジティブなランドスケープ設計)を通じ、都市空間そのものが自然資本の一部として機能する未来像が拓ける。例えばアムステルダム東部の人工島群から成る新興住宅地区のIJburg(アイブルフ)では15、水上住宅と湿地帯を併設し、住民が生物多様性モニタリングをゲーム感覚で行う仕組みを導入している。ハードとソフト双方のレジリエンス向上が資産価値を押し上げ、平均取引価格は市域平均を10%以上も上回った。

アムステルダム東部の新興住宅地区・IJburg(アイブルフ)の水上住宅
シンガポールのLCNGグループは「Punggol Digital District」16の190haのエリアを開発する過程で、既存マングローブを2倍に拡張し、雨水を潟湖に貯留するブルーグリーン・インフラを採用。建物は全棟マスティンバー(集成木材)でCO₂排出を40%削減し、同地区の地価は近隣平均比15%上昇した。

Punggol Digital District
旅行・観光分野では、地域の自然環境をただ“見る”対象ではなく、“共に再生し体験する”関係へと変える再生型エコツーリズムが世界的に台頭しており、日本の里山や海洋生態系も大きな可能性を秘めている。たとえばニュージーランドでは Tiaki Promise17(マオリ語で、ニュージーランドを大切に守り、未来の世代にも繋げていくための約束)に基づく植林・海岸清掃への参加率が28 %に到達した。またハワイでは Mālama Hawaii 18(伝統文化や自然環境を守ろうとする活動)に登録したホテルが宿泊 1 組ごとに固有種保護費を拠出し、年間 1.2 万本の在来樹を植樹した。
医療・介護分野では、たとえば米最大の統合医療組織 Kaiser Permanente19(カイザー・パーマネンテ) は、診療圏内の緑被率を健康指標に組み込み、緑地が最も少ない四分位地域の医療費が年間 1人当たり平均260 ドル高いと定量化した。このデータを逆手に取って「Green Spaces & Cool Food」プログラムを開始、病院調達を再生型農産物へ切り替え2030年までにフード由来温室効果メタンガスを25 %削減目標とし、2023年時点で14 %を達成。施設内外の生態系回復、医療収支の改善、財務メリットを同時に可視化し、自然資本を医療ビジネスの競争力に転換している。
アパレル分野では、Stella McCartneyはバイオ素材や再生繊維を採用し、自然再生型サプライチェーンの構築を推進している。こうした動きは、単なる「エコ」ではなく、ブランドの文化的価値や顧客との共創関係を再構築する戦略へと進化している。LVMHは「Life 360」戦略20で素材原料調達地の生態系スコアをQRコードに埋め込み、顧客がカメラで読み込むと植生変化の衛星画像が再生される仕組みを導入した。希少性の源泉が“破壊できない自然の物語”へと移行した瞬間である。
ビューティー分野では、単なるグリーンイメージの演出ではなく、ブランドが自然再生にどのように関与しているかを透明に開示し、体験として提供する”ネイチャーストーリーブランディング”が新たな価値軸となる。一例として、豪州コスメ「Aesop」が挙げられるだろう21。同社は原料サプライヤーの生態系回復ストーリーを長期ドキュメンタリー化し、取引農園の生態系復元や長期リジェネラティブ契約を公式に公開している。ブランド体験の時間軸を「製品寿命→生態系寿命」へ拡張する試みである。
飲食サービス分野では、再生型農業による地元食材を用いた店舗運営や、海洋資源の回復とリンクしたシーフード提供が“食べることで守る”という消費行動を支えている。たとえばイタリアのSlow Food運動などがその先駆けである。ピエモンテはリジェネラティブ・キュイジーヌの先進地域で、五つ星リゾート Casa di Langa22 は敷地のうち約3,000 ㎡を雨水100%利用のバイオダイナミック菜園に充て、レストランが使用する野菜・ハーブを自給。また宿泊者はガーデンツアーで収穫体験と料理教室に参加できる。循環型農法の成果が来館体験へ直結し、同リゾートは2024年にGreen Globe 認証を取得した。
またカナダBC州は資源枯渇対策として沿岸164か所にロックフィッシュ保護区(RCA)を設置した。10年で産卵親魚指数が平均3倍に回復した区域のみ限定漁獲を解禁し、漁獲物はOcean Wise®認証でブランド化して流通させた。バンクーバーのシーフード店「Coast」は認証ロックフィッシュを限定メニューで提供し、売上の5%を保護区管理基金へ寄付している。客はQRコードで産地座標と資源データを確認できる、資源回復、ブランド価値、保全資金循環を一体化した再生型シーフードモデルの例である。23
こうした再生型事業の取り組みにおいては、デジタル技術の活用も欠かせない。プラスチック回収をブロックチェーンでトークン化する「Plastic Bank」 24はその代表例だ。ハイチ・インドネシア・フィリピンなど沿岸14 か国で、回収業者がスマートフォンアプリに重量と写真をアップロードすると、量に応じて 「Social Plastic®トークン」 が即時発行され、モバイルマネーで現金化できるしくみだ。企業はトークンを購入することで“海洋流出プラ削減クレジット”を取得し、製品に表示できる。2024年末までに累計10.8 万名の登録回収者が、30億本相当(約120万 t)の海洋プラスチック流出を防止。加盟ブランドは SCジョンソン、ヘンケル、花王など50社超に拡大し、トークン売上の一部は沿岸インフラ整備や子どもの学費補助に再投資される。デジタル台帳によるトレーサビリティが、廃棄削減・貧困削減・ブランド価値向上の三位一体効果を実証しているケースである。

Plastic Bankでは世界各地の沿岸地域に住む人々にプラスチックごみの回収をしてもらい、その対価としてデジタルトークンを払う
「地方創生」ではない、自然資本を核としたローカル発の事業戦略のあり方
特筆すべきは、このような自然資本の再生型ビジネスが、都市型経済よりむしろローカル経済の中で生まれやすいという事実である。都市部では自然資本との接点が乏しいが、地方には森林、河川、農地、沿岸など、未利用または低利用の自然資源が広がっている。
じっさい、日本は国土の約70%が森林であり、豊かな水系、里山、沿岸生態系を持つ自然資本大国である。しかし、その多くは未活用・放置状態にある。林業は採算性が低く、農業も高齢化と耕作放棄地に悩む。漁業は乱獲と資源管理の失敗に直面しており、三大一次産業はいずれも構造的な危機にある。
この背景には、自然資本を単なる「資源=採るもの」として捉える発想の限界がある。自然を搾取対象とするのではなく、共生し、再生し、価値を共に創るという視座に転換しなければならない。地方こそが、「自然×経済」の実験場であり、再生型経済の最前線なのだ。
日本では、環境保全や地域活性の取り組みがしばしば「CSR」「地方創生」「補助金プロジェクト」として語られてきた。しかし、これらは本業と切り離された一過性の活動になりがちであり、持続的価値を生まないことが多い。発想を変えて、自然資本を「未来志向のビジネスモデル」として捉えるということが重要だ。それは、以下のような視点である。
- 地域の課題解決=競争力の源泉として設計する
- 再生プロセスが差別化要素となる商品・サービスを展開する
- 自然保全がコストではなく利益の源になる構造をつくる
たとえば、再生型農業による高付加価値農産物を提供し、炭素クレジットも創出するモデル。間伐材を用いた地域建築で森林の循環と住宅需要を繋げる事業。藻場を再生して魚の産卵場を回復させながら、ツーリズムや教育と結ぶ海洋地域活性事業を展開するなどの取り組み。いずれも、自然の再生が“経済価値”として成立する仕組みを取り入れている。
自然資本の価値を、消費者にどう伝えるか
一方で、自然資本を基盤とする事業が真に社会に根づくには、消費者がその価値を“自分ごと”として理解し、付加価値を払うなどの支持する構造が不可欠である。いかに再生型の取り組みが優れていようとも、それが消費者の共感や選好に結びつかない限り、持続的な市場形成は難しい。
先の各分野での事例にもあるように、ここで重要なのは、「環境に良いから買ってください」という道徳的訴求を超えた、機能価値・物語価値・参加価値の三層でのアプローチである。
- 機能価値:再生型農業の野菜は味が濃く、栄養価が高い。間伐材の家具は湿度調整や空気清浄の機能を持つ。自然資本を生かした製品の物理的品質を、正しく可視化し伝えることが第一である。
- 物語価値:誰が、どの自然環境と関わり、どのような再生のプロセスを経て商品が生まれたのか。それを映像、データ、ストーリーテリングで表現し、そして体験を通じた共感の導線を築くことが第二である。
- 参加価値:購入することが自然再生への貢献であり、自らの生活が地球環境とつながっている実感を得られ、さらに活動に参加できる仕組み(例:商品購入でマングローブ1本植林など)を設けることが第三である。
消費者を「最後の受け手」ではなく、「循環に参加する主体」として位置づけ直すことが、再生型資本主義のマーケット形成において鍵となる。
風土資本と感応経済――自然資本“以後”の価値軸
自然資本を損なうことで拡大してきた経済は、もはや持続可能ではない。今後の企業、地域、そして国の繁栄は、「いかに自然資本と共に価値を創出するか」にかかっている。それは成長の放棄ではなく、成長の再定義である。「成長=量的拡大」から「成長=質的進化」へと転換するための道筋として、自然資本と再生型ビジネスの融合は不可避である。
もう少し議論を先に進めていこう。自然資本を「守るべき資源」や「経済の土台」と捉える段階は、まだ出発点にすぎない。次に問われるのは、「自然資本の回復」が経済の目的となったとき、次の議論となるのが人間社会と市場、そして“価値”の意味がどう変質していくかという問いである。
第一に、自然資本はもはや“計測される対象” ではなく、“関係性を設計する場”へと転換する。炭素吸収量や保水力だけでなく、「その土地の自然と人の感性がどうつながるか」を編集・デザインできる企業が生き残る。たとえば地域の風景や音、香り、景観を価値としてパッケージ化する「風土資本」の発想は、単なるエコツーリズムを超える文化経済の構想である。
第二に、企業は「環境を再生する経営人格」を持たねばならない。これからの企業やブランドは、単に環境負荷を減らすのではなく、「環境と倫理に応答する主体」としての構造変化が問われる。これはサステナビリティ担当部門の拡充ではなく、経営そのものの人格化であり、パーパス経営の本質でもある。
第三に、自然資本を“ひとくくり”にするのではなく、「流域資本」「風土資本」「生態記憶資本」といった多層のレイヤーに分解し、地域や人の関与の中で意味を再編集する視点が求められる。たとえば京都の景観協定やスイスの音景保護条例のように、自然を“制度でも市場でもない第三の場”で扱う仕組みづくりが、これからの都市・地域計画において鍵を握る。
自然資本の未来は、単に持続可能であることではなく、「意味を持ち、関係を結び、人格として共に生きる存在としての自然」と経済がどう共創できるかにかかっている。そのビジョンを描ける国や地域、企業こそが、次の時代の希望となるだろう。
(タイトル画像はPunggol Digital District:JTC)
脚注:
- オーストラリアではタスマニア島の東岸沿いで巨大ケルプ森林の約 90〜95 % が過去半世紀で失われた(Johnson et al. 2011;DPIPWE 2015) ↩︎
- Hallmann C. A. et al., More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas, PLOS ONE 12(10): e0185809 (2017) ↩︎
- ジョン・フラートン:https://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Fullerton ↩︎
- ロデール研究所 FST 40年報告によれば有機・再生農法は平均 5-10 %高収量、干ばつ年は 30 %超(Rodale Institute 2020)。同レポート付録の換算式を用いれば、土壌有機炭素 1 %上昇で 1 ha 当たり約 210 t の保水力向上となる。 ↩︎
- UPM の Natural Capital Impact Assessment(2019)と年次報告 2023 によれば、フォレスト・バランス経営により 5 年で森林資産価値は 14 %増、株価リスクプレミアムも同業平均を下回った。 ↩︎
- TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース):https://tnfd.global/ ↩︎
- https://pollinationgroup.com/climate-asset-management/?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- パタゴニアは Tin Shed Ventures™ を通じて Edacious などソイルフードウェブ関連スタートアップへ出資し、農家の ROC 転換費用をプレミアム前払いで支援している Tin Shed VenturesRegenerative Food Systems Investment Vogue Business ↩︎
- Blue Ventures 公式 “Locally‑Managed Marine Areas” (2024) 沿岸コミュニティが自主的に休漁区を設置し、水産資源回復後にローカルブランドで輸出(UNEP‑WCMC 2022)。 ↩︎
- Indigo Ag:https://www.indigoag.com/ ↩︎
- Suzano:https://www.suzano.com.br/en ↩︎
- SeaChange ® 360:https://www.waste360.com/plastics/seachange-s-new-tech-will-save-the-oceans-from-plastic-waste ↩︎
- Ørsted:https://orsted.jp/ ↩︎
- JapanGov “Plant‑Derived Material Will Change the Future of Automobiles” (2021) :NCVコンセプトカー。セルロースナノファイバー部品化で車両 LCA CO₂ 削減を実証(JapanGov 2021) ↩︎
- Amsterdam “Green Infrastructure Vision 2050” (2020) ・ MDPI “Nature‑Based Solutions in Urban Areas” (2023):IJburg 湿地帯・水上住宅整備と住民アプリによる生物多様性モニタリングを自治体ビジョンで提唱(Amsterdam 2020) ↩︎
- Punggol Digital District:https://estates.jtc.gov.sg/pdd ↩︎
- Tiaki Promise:https://www.newzealand.com/jp/feature/tiaki-care-for-new-zealand/ ↩︎
- Mālama Hawaii :https://www.gohawaii.com/malama ↩︎
- Kaiser Permanente:https://healthy.kaiserpermanente.org/front-door ↩︎
- LVMH “LIFE 360 Roadmap” (2023):原料トレーサビリティと生態系スコアを QR で可視化する方針を公表 ↩︎
- Aesop Sustainability Hub/“Kyklos” (2024):Aesop は原料農園の生態系回復を長期ドキュメント化し、購入者が寄付投票に参加できる仕組みを公表(公式サイト) ↩︎
- Casa di Langa:https://www.casadilanga.com/ ↩︎
- https://www.glowbalgroup.com/coast/ ↩︎
- Plastic Bank:https://plasticbank.com/ ↩︎
























