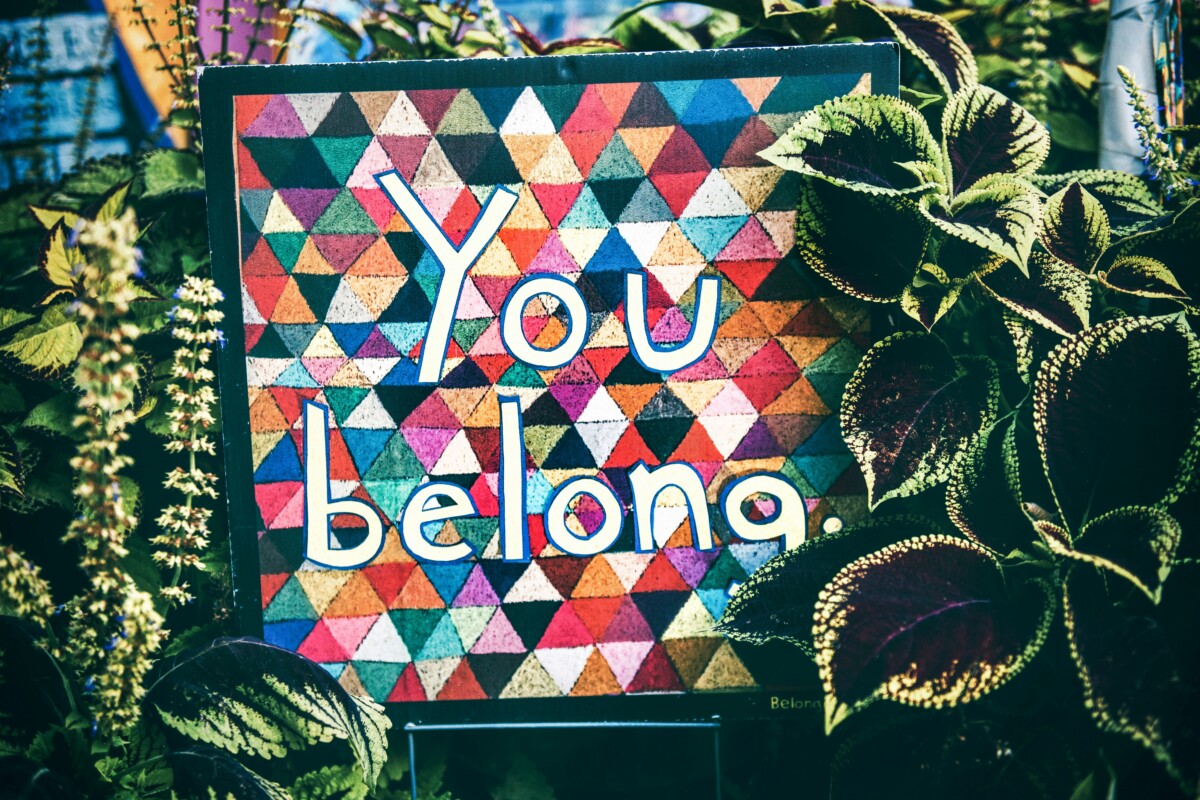
「麻痺状態」のインクルーシブ・マーケティングをどう打開するか
変化の激流といまの停滞
この5年で、広告における多様性の位置づけは大きく揺れ動いた。2020年以降、多くの企業がDEI(ダイバーシティ/エクイティ/インクルージョン)を掲げ、専門責任者の配置を拡大したが、その後の縮小や役割廃止も相次いだ。社会・政治情勢の反動も重なり、ブランド側には「何をもって包括とするか」を定義しきれず、意思決定が滞る“麻痺感”が広がっている。E.l.f. Beautyの「So Many Dicks」など、経営層の多様化を訴える施策が注目を集める一方、実装の継続性と一貫性は依然として課題である。
業界の足踏みを示すデータ
XRとThe Female QuotientによるAI分析(約100万本、35業界)では、世界平均の表現度に満たない業界が半数超という結果が示された。Samba TVのレポートでも、非白人タレントの露出が前年比で後退し、ヒスパニック系の起用や到達にギャップが残っていることが浮き彫りになった。全米広告主協会の集計では、マーケティング業界における有色人種比率が2023年に低下し、労働力の多様性も頭打ちの兆しが見られる。
DEI縮小と世論の反発が生むリスク
一部の大手企業はDEI投資を絞り込んだ結果、コミュニティ側から「置き去り」にされた感情が広がり、広告表現にもその歪みが投影される事例が出ている。逆に、表象の拡大に踏み込んだブランドが、政治的反発やボイコットの標的になることもある。短期のムードや“流行”に合わせて価値観を変える姿勢は、長期的な信頼を損ないやすく、ビジネスへの悪影響につながる。
物価高や不確実性のなかで、消費者は「価格×価値」の釣り合いに敏感である。価値観を示す発信の重要性は否定しないが、品質期待に応えることがまず前提という捉え方が強い。結果として、価値訴求は“付加”ではなく、製品・サービス体験に埋め込まれた一貫性として問われている。
機会の大きさと“総花”の限界
最も成長が見込まれる消費市場は多様なオーディエンスであり、購買力は巨額にのぼる。消費者の多くはブランドのD&I評判を行動指標として参照しており、自己を映す表現を強く求めている。重要なのは、すべての人に同時に応えようとするのではなく、狙うグループを明確に特定し、その接点(商品、流通、広告、接客、サポート)を貫く一貫性を設計することにある。
データで可視化し、現実に近づける
表現ギャップはデータで特定できる。例えば、肌の色が濃いタレントを起用していてもスクリーンタイムが相対的に短い、広い肌色レンジのキャスティングが偏る、といった偏差は測定可能である。一方で、属性データだけでは個人のアイデンティティや文脈を捉えきれない。定量と没入的な定性理解(コミュニティとの対話・共創)を併走させることが、解像度を高める近道である。
クリエイターとコミュニティの力を戦略に結び込む
クリエイターは、忠実なコミュニティとの橋渡しに有効である。インフルエンサーマーケティング投資は拡大が見込まれるが、起用は単発露出ではなく、ブランド戦略に適合する“長期関係”として設計することが肝要である。炎上事例に学ぶべきは、雑音を恐れて沈黙することではなく、目的・対象・表現の整合性を高め、やり抜く一貫性である。
実装のための実務ガイド
- コア定義の明確化:包括(インクルージョン)とは何か、誰に対して何を約束するのかを経営レベルで明文化し、意思決定とKPIに落とし込む。
- ベースライン測定とギャップ特定:起用・表現・露出・体験の各KPIを分解し、スクリーンタイムやクリエイティブ内の役割、顧客接点での体験差を計測する。
- 意図的な優先順位付け:ターゲット群を明示し、プロダクト開発から流通、コミュニケーションまでの優先投入順を決める。
- クリエイティブの多層化:年齢、体型、肌色、障害、出自、家族構成など多面的表現を“統一トーン”で継続。特定イベント期のみの“出没”を避ける。
- ガバナンスと安全網:レビュー体制、危機対応、地域差・法規差の考慮、学習ループ(テスト→測定→改善)を運用に組み込む。
- 現場への移植:代理店・制作・小売・カスタマーサポートまで同一原則で教育・評価を行い、現場の意思決定とインセンティブを接続する。
最も疎外されてきた人々を起点に考える
インクルージョンは“施策”ではなく“生活と機会”の問題である。黒人・褐色人種、LGBTQ+、障害のある人々、先住民など、歴史的に排除されやすかったコミュニティの視点に立ち、表現と機会の連鎖を変えることが、長期の成長と信頼をもたらす。ブランドは集団としての声を受け止め、個の尊重を日常の決断へ翻訳することで、行き詰まりを前進へと転じることができる。(出典:Marketing Dive)
















