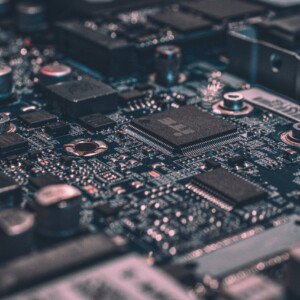BYDのグローバルブランド戦略─EV覇権をめぐる劇的な業界再編
はじめに:EV覇権をめぐる構図の変化
世界の自動車産業は、100年に一度の変革期にある。EV(電気自動車)化の波は産業構造の根底を揺さぶり、既存のブランドヒエラルキーを再編しつつある。そうした中で中国のBYD(比亜迪)は、単なる「EV台数1位企業」ではなく、新たなグローバルブランド像を構築しようとしている。
テスラのようなカリスマブランドでもなければ、日本車のようなロングセラー型の堅実路線でもない。その中間にありながら、次代を制する革新性と柔軟性を併せ持つ存在として浮上している。
2023年にEVとPHEV(プラグインハイブリッド車)の年間販売台数で世界一となり、2024年にはさらに40%以上成長し、自動車販売台数全体でもホンダ・日産を抜いて6位になった。しかも、BYDはEVのみならず人気のPHEVの売上が248万台と、トヨタの世界販売台数15万台を桁違いに上回っている。今後EV化がさらに進む中で、成長市場のシェアで圧倒的な優位性を誇っていると言える。
中国のクルマなんて信頼できなくて、と思う人が日本ではまだ多いようだが、その偏見が時代の変化への気づきを遅らせている。実際にBYDの最新の車種に乗ってみると、日本車と全く遜色ない(場合によっては超える)品質水準を達成していることに驚くだろう。このように市場戦略、価格と品質のバランス、グローバル展開のスピード、そして設計思想において独自のポジショニングを確立した今、BYDは製造業からブランドビジネスへの転換を進めている。
テスラが“未来のテクノロジー”を体現するブランドであるならば、BYDは“現実に根差した未来”を提供するブランドである。本稿では、BYDがいかにして世界市場でブランドとしての存在感を高めているのかを具体的に分析する。
ブランドの起点──技術革新性と自己完結型のエコシステム
BYDはバッテリー技術を核にした垂直統合型企業である。リチウム鉄リン酸(LFP)ベースの「ブレードバッテリー」は、安全性・寿命・コスト効率の面で世界的な評価を受けており、同社のブランド信頼性を構築する基盤となっている。例えば、実際に世界のスマートフォン約1/3がBYDのバッテリーを使っている。
この自己完結型のエコシステム──バッテリーから半導体、モーター、制御ソフトまでを内製する体制──は、サプライチェーンの乱れに強く、テスラのような外部調達型とは異なる競争優位を形成する。また、日本メーカーが培ってきた「品質管理による信頼性」とは異なり、「設計から製造までの一体化による最適化」によって信頼性を確保するという、新しいロジックである。
BYDは2025年3月、新たな「スーパーeプラットフォーム」を発表した。この新プラットフォームは、わずか5分間の充電で約400kmを走行できるというもの。EVの最大の弱点であった充電時間の問題を解決し、ガソリン車並みの利便性を実現する画期的なシステムであり、今後EV普及の決定的な要因となる可能性がある。
さらにBYDの事業はバッテリーを核に、EVおよびプラットフォーム、ITエレクトロニクス、都市交通、蓄電池などに広がっており、今後のスマートシティ化の中核的な領域に先手を打っているのだ。BYDは最近、最新鋭の運転支援システム(SDV)である「天神之眼」を大半の車種に追加費用なしで装備すると発表した。BYDはテスラと同じくSDV技術で世界の先頭を走っており、テスラはオプションで高価なSDVシステム導入を提供しているのに対しても、大きな優位性を実現しているのだ。
BYDのブランドコア
BYDのブランドコアは、「Build Your Dreams」という企業スローガンに端的に示されている。これは単なる夢想ではなく、“人々の現実的な未来生活をテクノロジーによって拡張する”という意志表明である。そこには、EVを通じて「サステナブルな移動」を可能にするだけでなく、「人と社会をつなぐ、スマートなライフインフラを構築する」というビジョンが込められている。
このブランドビジョンは、以下の3つの軸で構成されている。Technology-first: 自社開発によるバッテリー、半導体、モーター制御などのコアテクノロジーにより、信頼性と安全性を基盤にする。Eco-smart: 持続可能性を単なる環境アピールにとどめず、エネルギー循環型の社会インフラ構築を指向。Human-centered: UI/UXや車内空間、インフォテインメントの設計において、機械ではなく“人間の快適性”を中心に置く。
BYDのブランドは、単なる製品志向ではなく、「暮らしと社会に関わる存在」としての立ち位置を意識的に確立しつつある。
デザインと言語──欧米的審美感と“ブランド言語”の確立
BYDは、近年急激にデザイン品質を高めてきた。その象徴が、元アウディのデザイン責任者ヴォルフガング・エッガー(ジウジアーロに師事した、世界的なトップ・カーデザイナー)の起用である。彼の指導の下、「Dragon Face」というアイデンティティが全モデルに反映され、いわば“顔の統一”によるブランドの視認性を高めている。この意匠は、LEDヘッドライトのライン、グリルの形状、フロントバンパーの立体感といった要素を通じて、ドラゴンという東洋的象徴をモダンに再解釈したもので、見る者に強い印象を与える。

欧州車において、フロントグリルの形状がブランドの象徴であるように、BYDは中国企業として初めて、デザインを言語化し、視覚記号として統一的にブランドを訴求するフェーズに入った。
加えてロゴの刷新も重要な転換点である。旧来のBYDロゴは楕円形の中に文字を配置した伝統的なデザインであったが、2022年以降のモデルではロゴをフロントからあえて排除し、エンブレムレスにする手法が採用されている。これはAppleやTeslaと同様に、「機能美がブランドを語る」という思想に基づいており、製品自体がアイデンティティとなる。
車名のネーミング戦略も、英語圏のユーザーにとって認識しやすい「Dolphin」「Seal」「Han」「Tang」など、自然・歴史・神話に由来する象徴的な単語を用い、直感的な印象を与える設計となっている。これにより、グローバル市場でもブランドが視覚・音響的に“記憶に残る”よう設計されている。
BYDは「記号としてのデザイン」「語彙としてのネーミング」をブランド構築のツールとして意識的に活用しており、言語的・視覚的記憶に訴えるブランドアプローチを確立しつつある。また、ウォルフガング・エッガーによるデザインは、欧州的審美感と東洋的象徴性の融合を図っている。デザインそのものが文化の境界を越える装置として機能し、ブランドを世界に伝える“記号言語”としての役割を担っている。
“アフォーダブル・プレミアム”という新たな市場創造
EV市場は、従来「プレミアム=テスラ」「低価格=中国の小型車」のような二極構造にあった。しかしBYDは、その中間にあたる“アフォーダブル・プレミアム”という新たなゾーンを開拓しつつある。
たとえば、「Dolphin」や「Seal」は、日本円で300万円前後という手が届く価格帯ながら、インテリアの質感や装備、安全性能において、欧州車に匹敵するレベルを備えている。特に欧州市場では、「価格に見合わぬ高級感」「スマートフォンのようなUI/UX」「余裕ある航続距離」といった点で、“お得感のある先進車”として評価されている。
この「価格に見合わぬ魅力」は、かつてトヨタが「コロナ」「カローラ」で達成したブランド戦略を彷彿とさせる。だが重要なのは、BYDがそれを意図的かつデジタルネイティブな世代に合わせて設計している点である。
また、サブブランド「Yangwang(仰望)」によって超高級EV市場にも進出しており、価格帯の“逆三角形化”を図っている。これにより、「低価格=低品質」という旧来のブランドバイアスを打破し、全価格帯での信頼を築こうとする動きが明確である。
日本車との対比で見ると、トヨタやホンダのEVが価格と内容のバランスで中途半端な印象を持たれがちであるのに対し、BYDは価格と価値の乖離を“意図的に操作”してブランド価値を高めている。この差は、ブランドの「知覚価値(Perceived Value)」のマネジメント能力に直結している。
特に注目すべきは、プレミアムサブブランド「仰望(Yangwang)」や、スポーツEVブランド「Fang Cheng Bao(方程豹)」を通じて、“テクノロジー×ラグジュアリー”という価値軸を再定義しようとしている点である。

プレミアムサブブランド「仰望(Yangwang)」
これは単なる価格帯の拡張ではなく、「中国らしい美意識と先進性が両立するブランドは可能か?」という問いに対する実験でもある。BYDは、この問いに対して真正面から挑戦し、「メイド・イン・チャイナ」ではなく、アップルのiPhoneのように「デザインド・イン・チャイナ」「ブランディッド・バイ・チャイナ」への転換を図っている。
現地化戦略──スピードと柔軟性の地域別展開
BYDのグローバル戦略におけるもうひとつの注目点は、各国ごとに異なる制度・ニーズに対応する「現地化」の徹底である。新興国を中心にしたグローバル展開戦略とともに、すでにブラジル、ハンガリー、タイ、インドネシア、ウズベキスタンなどでの生産拠点立地を発表しており、「工場を持つこと=市場での信頼」となる国々で戦略的に展開している。
特筆すべきは、「単なる生産移管」ではなく、「サプライチェーン構築」「EVインフラ支援」「官民連携の枠組み」まで含めた包括的展開である。EV市場は単体の製品力では勝てず、充電網・部品調達・人材育成などを含めたエコシステム構築が不可欠である点をBYDは理解している。
たとえばハンガリー工場の開設にあたっては、単なる生産拠点としてではなく、「地域の未来を担うブランド」として政府と教育機関とのパートナーシップを締結している。これは、BYDを「インフラの一部」として受け入れてもらうための、意味づけのブランディングである。この「信用を構築してから消費者にアプローチする」という姿勢は、日本企業が得意とした“信用ベースの長期戦略”を、今や中国企業がより高速で遂行しているという逆転の構図を示している。
BYDは日本や欧州でも「乗用車」ではなく、まず「電動バス・商用EV」の導入から信頼を積み上げ、その後にコンシューマー市場に参入するという順序立てられた展開を採っている。現在日本の電動バスの70%以上がBYD製であるのをご存知だろうか。日本市場でも2025年中に販売店を100店舗体制に拡大、日本だけの軽自動車EVも導入するという、矢継ぎ早な発表が最近あった通り、柔軟でスピーディーな現地展開を図っている。また、ライドシェアのUberやGrab提携して、10万台規模のEV導入を進めており、EV単体ではなく移動システム市場からの参入を強化し、ブランドのプラットフォーム化を拡大しつつある。
ブランド体験の構築:テクノロジー主導からUX主導へ
BYDが従来の中国車と大きく異なるのは、「製品スペック」だけでなく、「体験設計」に注力している点である。
まず、インテリア設計では大型回転スクリーンを全車種に搭載し、タッチ操作と音声コマンドによるUIの一体化を実現している。インフォテインメントには自社開発のDiLink OSを使用し、アプリの拡張性やソフトウェアアップデートを通じて車両が進化する設計になっている。また、4つの車輪に独立したモーターを搭載した「e4プラットフォーム」を採用。それぞれのタイヤをコントロールすることができるため、独自の「スライド縦列駐車」や、車体を「360度回転」させるタンクターンを可能としている。

また、乗り心地や静音性、空間構成においても従来の「技術偏重型」ではなく、五感に訴えるUX重視のプロダクト設計がなされている。たとえばEV特有の無音性を活かし、走行音・通知音をブランド独自にカスタマイズしており、音響設計までブランド体験に取り込んでいる。
加えて、試乗・納車・アフターサービスのプロセスにおいても、オンライン接客やスマートショールーム、モバイルアプリによる予約管理など、ユーザーとのタッチポイントを“ブランド体験”として一貫化している。これは、単なる「所有」ではなく「参加型体験」としてブランドに接続する仕組みであり、EV時代にふさわしいリテール戦略といえる。
BYD SEALION 7 | イメージムービーより
「メイド・イン・チャイナ」から「チャイニーズ・プレミアム」へ
長年、世界市場において「中国製」は安価・模倣・信頼性に欠けるという負のブランドイメージと結びついていた。だが、BYDはこの認識を逆手に取り、戦略的に“ブランド刷新”を試みている。
ひとつは、スポーツやエンタメとのコラボレーションである。2023年にはイタリアのセリエAクラブやドイツのF1電動レース「フォーミュラE」へのスポンサーシップを通じて、若年層へのリーチを強化。これはAppleやRedBullが得意とした“カルチャーとの接続によるエモーショナル・ブランディング”の応用である。特にサッカーはUEFA EURO 2024、UEFA U-21欧州選手権2025、またCONMEBOL コパ・アメリカ 2024へのパートナー・スポンサーシップを展開するなど、欧州や新興市場の南米など、特定の地域市場への影響力を高め、若年層を軸に次世代の顧客基盤を構築するためのスポーツブランディングを積極展開している。
もうひとつは、他ブランドとの戦略的連携である。BYDは日本のトヨタとEV共同開発(BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY)を進める一方、ライバルであるテスラやスズキとも連携・バッテリー供給を行っている。これは「敵と組むことで、自社の技術の信頼性を証明する」というPRでもあり、単なる商取引を超えて、信頼のレバレッジとしてのアライアンス戦略を展開している点が画期的である。
また、BYDは「自社のメディアコントロール」も重視しており、WeChatや微博(Weibo)を使った中国本土でのブランド統制に加え、欧米ではTwitterやYouTubeを活用した「現地発信」に注力している。これは従来の日本車が得意としなかった“リアルタイム・コミュニケーション型のブランドマネジメント”であり、ブランドの“距離感”を縮めることに成功している。
BYDはもはや“急成長する中国メーカー”ではない。自らを「テクノロジー×モビリティ×カルチャー」のブランドと再定義し、グローバルで統一されたブランド体験を設計する存在へと変貌している。従来の「コピー型中国ブランド」というステレオタイプを完全に脱却し、“オリジナリティ×国際性”を備えた新しいグローバルブランドとしての道を切り開いている。
その鍵となるのは、「ブランド=体験×関係性×象徴性」という三位一体の構造を、グローバルに実装していけるかどうかである。BYDは今、その可能性を最も現実的に示している存在である。テスラが未来を語る力を持ち、日本車が実直さを誇る中で、BYDは“機能性と意味性の中間”にあるブランドとして、最も広い市場を射程に入れている。ここに、次代のブランド競争の構図がある。
BYDのブランド戦略は、「技術的優位性」や「価格競争力」だけで説明できない洗練を伴っている。製品における一貫性、体験における心地よさ、表現における象徴性、そして世界の人々との関係構築。それらがブランドとしてのBYDを形づくっている。
BYDの成功は日本車メーカーにとって単なる脅威ではない。今後のブランド戦略において、単なる技術力や価格戦略を超えて、「どのような体験ストーリーを提供するか」「どのような文化的接点を作るか」という視点の重要性を示す、未来からの警告である。