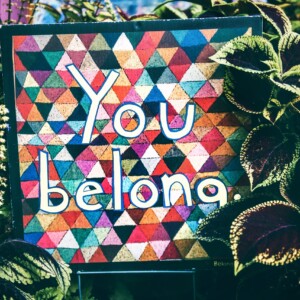アメリカのブランド価値の地殻変動—『希望の国』はどこへ向かうのか
国家ブランド価値の再構築と多極化する世界秩序
「アメリカ」は、かつて世界が憧れた理想であった。自由市場、民主主義、イノベーション、そして世界秩序の守護者としての立場。20世紀から21世紀初頭にかけて、アメリカの国家ブランドは、国家ブランドの頂点に君臨してきた。そしてまるでグローバル社会の指標のように機能していた。
だが、その輝きには明らかな陰りが差し込んでいる。民主主義の後退、格差の拡大、気候危機への無策に加え、2025年のドナルド・トランプ大統領による“経済的独立宣言”は、もはや決定的な地政学的転換点となりつつある。
この相互関税のエスカレートにより、米中は再び深刻な貿易戦争へ突入しつつあり、国際秩序は大きく揺らいでいる。このディール的手法は「勝者がすべてを取る」資本主義の帰結とも言えるが、その過程でアメリカは、他国からの信頼という無形資産を大きく損なった。
これは、単なる通商政策の問題ではない。それは、これからの社会の国家のブランドに求められる価値とは何か、という本質的問いを我々に突きつけている。以下、本稿では現実化したアメリカのブランド崩壊の意味を起点に、ヨーロッパ、中国、新興諸国における多極化するブランド価値の変容、さらにはディール型大国に抗する新たな国家ブランドの姿を論じてみたい。
国家のブランド価値とは何か
そもそも、国家のブランド価値とは何だろうか。それは、一つの国が国内外に対して持つ総合的な「印象」や「信頼」、人を惹きつける「魅力」などの要素のことであり、経済的、政治的、文化的影響力を持続可能に高めるための戦略的資産である。製品や企業ブランドと異なり、国家ブランドは多層的かつ複合的な構造を持つ。歴史や伝統、自然環境、政治制度、技術力、文化、国民の振る舞い、外交姿勢まで、その国に関わるあらゆる要素が長期にわたり積み上がって形成される。
例えばサイモン・アンホルトらが2005年に創設したナショナル・ブランド・インデックス(Anholt-Ipsos Nation Brands Index)1では、国家の「輸出力」「観光魅力」「投資と移住意欲」「ガバナンス」「文化遺産」「人々の好感度」の6指標をもとに国家ブランドを数値化している。国家ブランドが国際世論に与える影響、投資先・観光先・教育先としての魅力に直結することを統計的に示している。
国家ブランドが機能するのは、主に三つの局面である。一つ目は経済的便益である。ブランド価値が高い国は投資先としての信頼を得やすく、観光、輸出、人材獲得など多くの分野で競争優位性を持つ。たとえばスイスや北欧諸国は、国際的な信頼度の高さを背景に、金融、環境技術、教育などで高い付加価値を創出している。
二つ目は外交的影響力だ。信頼される国家は国際的な議論において発言権を持ち、国際ルール形成に関与しやすくなる。欧州連合(EU)が提示するデジタル規制や環境基準は、制度そのものが「ブランド」となって国際標準化を促進している。
三つ目は内政の安定と国民の誇りである。強い国家ブランドは国内にも正のフィードバックを与え、国民のアイデンティティや社会的結束を高めることで内政を安定させ、国民の誇りや忠誠心、社会貢献意欲を高める。たとえばパンデミック時における市民の協力姿勢は、内外に向けてその国の信頼を強化する契機となる。
このように国家のブランドとは単なるイメージではなく、戦略的に形成・維持されるべき無形資産であり、国家が持つ最も重要な“未来志向の競争力”と言えるだろう。
アメリカの自己喪失とブランドの空洞化
「民主主義」「自由」「イノベーション」——アメリカのブランド価値は、戦後の国際秩序の基盤であった。その民主主義の神話に決定的な亀裂を生じさせた出来事は、2021年1月6日に起こった法と民主主義の象徴・アメリカ議会襲撃事件であり、2025年4月の関税攻撃はその延長線上にある。アメリカは、関税による自国利益の最大化を図ることによって、市場価値の低下にとどまらず、信頼というより大切な通貨を喪失しつつある。
ジョセフ・ナイ2が説くソフトパワーとは、「他者を魅了し従わせる非強制的影響力」だが、近年のアメリカはむしろ「ハード・バーゲニング」(強硬な取引)に依存し、そのブランドイメージを毀損している。あなたの友人が、人を脅して強引な取引をするような人だったら付き合うだろうか。ビジネスの世界であっても、取引先の企業が相手を出し抜いて利益の最大化を狙う行動ばかりしていたら取引を続けるだろうか。こうした行為を世界のリーダーシップを保ってきた国家が行うという異常事態が、まさに現実に起こっていることだ。
ピュー・リサーチの調査(2024年)3によれば、「アメリカの民主主義はモデルたり得るか」という設問に対し、日本も含むG7諸国におけるアメリカへの信頼は50%を下回った。またPR会社エデルマンのトラスト・バロメーター調査(2025年)4によると、アメリカ政府に対する信頼はわずか1年で23%低下した。トランプ政権の政策は、短期的には「アメリカ第一」を印象づけるが、中長期的には「アメリカ孤立」を加速させている。
アメリカの国家ブランドを支えていたもう一つの柱が、シリコンバレーに象徴されるテクノロジー覇権である。グーグル、アップル、テスラ、メタといった企業群は世界経済の中心に位置してきた。実際、現在でもNASDAQ市場の上位企業の大半は米国企業である。
だがかつての“開かれた革新の聖地”はその魅力を失いつつある。テック分野でも、プラットフォーマーの暴走、AI倫理問題などにより、アメリカ発の技術革新はもはや無条件に歓迎されていない。
一方で、カナダのトロントやドイツのベルリン、シンガポールが新たなテックハブとして台頭し、多様性と制度的安定性を武器に世界中の才能を引き寄せている。また、AI関連特許申請数では中国がアメリカを抜き、国家主導の研究開発で圧倒的な数の成果を上げている。
これらの動きは、単なるイノベーションの地理的移動ではない。技術こそが価値創造の源泉である現代において、それは国家ブランドの根幹の移転を意味する。かつての「Made in USA」は、「Trusted in EU」「Invented in China」へと変容しつつある。

ヨーロッパ——倫理国家としての「制度のブランド」再構築
アメリカ的自由主義が退潮する一方で、ヨーロッパは「倫理」と「制度の信頼性」を軸に国家ブランドを再定義している。EUが推進するグリーンディールやデジタル市場法(DMA)、AI法などは、技術の暴走を法で制御し、公共性を優先する枠組みを提示するものだ。
イアン・マナーズが「21世紀のパワーは、規範を定義する力にある」5と述べたように、今やルールを作る力こそが国家ブランドの核となる。倫理的価値の輸出に成功したEUは、その制度そのものが「ブランド」として世界に広がっている。
また、ドイツ、フランス、スウェーデンといった国々では、循環型経済、カーボンニュートラル、人権デューデリジェンスといった理念が国是となっており、これは企業ブランディングや国家外交にも密接に結びついている。事実、2022年の国連SDGインデックスで上位を占めた国々はほぼ全て欧州であり、国際NGOによる人権評価やジャーナリズムの自由度でも一貫して高評価を得ており、世界からの「信頼のブランド」としての地位を高めている。
これらの国々は、GDPでは測れない「信頼される国家」というブランドを構築している。ユヴァル・ノア・ハラリは「未来は国家ではなく、価値観を共有するネットワークによって形成される6」と語った。ヨーロッパの国家ブランドは、まさにこの「価値のネットワーク」として再編されており、アメリカとは異なるモデルを提示している。
中国の国家ブランド——規律か信頼か
中国は、巨大な人口と統治機構、国家主導の技術革新を武器に「中国式現代化」をブランド化しようとしている。「発展こそ正義」という理念のもと、「一帯一路」やデジタル人民元などを用いて、自らのモデルを新興国へと拡張しようとしている。AI、電気自動車、再エネといった分野では圧倒的なスケールで投資を行い、国家ブランドとしての「効率と秩序」を体現している。
そしてHuawei、BYD、TikTokなどの企業が、世界的な市場シェアを獲得して経済プレイヤーとしての存在感は増しているが、これらは国家のブランド価値とは異なる次元の話である。
2025年4月の米中関税戦争では、中国政府は「最後まで戦う」と宣言したが、その背後には強権的な統治手法への世界的な警戒がある。香港・新疆問題、言論の自由、監視社会——いずれも「信頼」には繋がらない要素である。
思想家ハンナ・アーレントは、権力と暴力の違いをこう定義した。「権力は人々の間に生じる信頼関係であり、暴力はその不在に基づく7」。まさに中国は、経済的優位を得た一方で、アーレント的な意味での「信頼に基づく権力」を得るには至っていない。
人権・自由という普遍的価値への疑念が根強く、特に民主主義国では信頼されるブランドには至っていない。ニーアル・ファーガソンが指摘するように、「大国が内向きになると、世界秩序は新たな中心を探し始める8」。
多極化とポスト・ディール時代の戦略的価値観
その意味で、新興国の中で最も注目すべきは、インドやブラジルのように、民主主義と経済成長を両立させようとする国々である。彼らは「ローカルな課題からグローバルな価値を生む」という新しい国家ブランドの実験場となっている。
トランプ的ディール国家が再び世界を揺るがす中で、各国は「対ディール戦略」として、持続可能性・公共性・連帯という新たな価値観を模索している。特に、インドやブラジル、インドネシアといった新興国は、自国の社会課題に即したローカルナラティブを用いて、独自の国家ブランドを育てている。
たとえばインドは、ジャガンナート政権が進める「デジタル・インディア」政策を通じて、グローバルサウスの技術革新と社会包摂のモデルを提示している。これは単なる経済戦略ではなく、ディール型国家に対抗する「倫理的かつ現実的」ブランド戦略であり、「デジタル民主主義大国」としてのイメージを強化している。
また、アフリカ諸国では「自立と共生」をテーマにしたブランド戦略が目立つようになった。ナイジェリアでは「文化経済(Creative Economy)」を軸に若者中心のナショナル・アイデンティティが再構築されており、ブランド国家はもはや国家だけでなく、市民との共創によって生まれるものとなっている。

環境変化と国家ブランド価値のシフト
アメリカが掲げてきた「自由市場」「民主主義」「イノベーション」といったブランド価値は、近年の地政学的な停滞や国内分断、技術覇権競争の激化に伴い揺らいでいる。その中で、以下のいくつかの変化シナリオが考えられる。
アメリカが築いてきた価値が相対的に弱まるにつれて、中国を中心とした「権威主義的な資本主義」の存在感が増している。中国は自由市場より国家主導の資本主義を推進し、民主主義ではなく「発展と安定」を優先しながら、技術革新を通じてグローバルな影響力を広げつつある。さらに、中東・アフリカなど新興国では、民主主義を必ずしも伴わない経済成長モデルが支持されるケースもある。そうした中で、中国が唱える「発展を通じた安定」という新たな世界秩序の概念が一定の支持を得る可能性がある。
また、ヨーロッパは民主主義や人権尊重を掲げつつも、環境問題や格差是正などを重視する「持続可能性」を軸とした新たな価値観を提唱し、世界的な影響力を強めている。自由市場万能主義に代わり、持続可能性や社会的公正を重視した経済モデルが注目されることも考えられる。
こうした変化が顕在化しつつある中、すでに起こりつつある代表的な国家のブランド価値のシフト・多様化は以下の通りである。
- 自由市場 → 制御された市場(ステート・キャピタリズム)
- 民主主義 → 安定重視の統治モデル
- 技術革新 → 社会的・環境的持続性への重心シフト
- 世界秩序の守護者 → 地域的な秩序の形成者
結局のところ、アメリカが支えてきた従来の価値体系は「完全に消滅」するのではなく、他の新たな価値体系と共存し、競争するようになると考えるのが現実的である。
アメリカが築いてきた価値体系(民主主義、自由市場、個人主義)、EUが推進する社会的公正や持続可能性を重視したモデル、そして中国や新興国が提示する権威主義的な資本主義や国家主導型モデル。これらの異なる価値観が多極的に競争・協調しながら共存し、「普遍的」とされていた価値が相対化・多元化されることが今後の主流となっていく可能性が高い。
すなわち、価値が一つに収斂するのではなく、複数の価値が並立し、多様な価値体系間で競争と相互影響が生じる世界が、アメリカ後の世界秩序のリアリティとなるだろう。
未来の国家ブランド——『強さ』より『共創』力へ
トランプのディール主義が示すのは、交渉を通じたゼロサムの勝利である。だが、こうした環境変化を超えて未来の国家ブランドにおいて求められるのは、ゼロサムを超えた「共創的優位性(co-creative advantage)」である。
その要となるのが、以下の3点である。①多国間で共通言語となるビジョンを提示できる力(共感性)、②制度の透明性と倫理的信頼性(倫理)、③イノベーションの社会実装力(創造性)である。この三位一体の価値があってこそ、トランプ的ディール国家に対抗しうる「ブランド資本」が形成される。
なぜ「共感」「倫理」「創造性」が重要なのか。それは、これらが単なる道徳的美徳ではなく、他国と関係を築く際の“可視化可能な比較優位”だからである。ディール型国家の強さが一時的であるのに対し、共感は持続性を、倫理は信頼性を、創造性は革新性を象徴する。
たとえば、北欧諸国が世界中のスタートアップ、研究者、移民から注目されるのは、福祉や倫理的規範が整っているからだけではない。自らが社会実験の場として機能し、創造性を刺激する環境を提供しているからである。国が「試す価値のある未来」を提示できるか——それが今後の国家ブランドの核となる。
この視点から、日本はどうあるべきか。日本は「協調」や「調和」の価値を長く育んできたが、それを単なる“受動的平和主義”にとどめるのではなく、より積極的に世界に提案できる「アクティブ・ハーモニー」へと進化させるべきであろう。気候変動、AI規範、持続可能な都市設計——これらの分野で日本はまだ多くの潜在力を秘めている。
加えて、超高齢社会における包摂モデル、職人文化を起点とした「人間中心の技術」、そして地域と都市が共に生きる分散型社会の設計——日本は、成熟国家だからこそ示せる未来像を持ち得る。
今後、国家ブランドとは「何を持っているか」よりも、「何を生み出せるか」、そして「誰と共に描けるか」が問われる時代となるだろう。過去の勝者たちは、資源や武力、GDPの大小でその地位を得た。だがこれからのブランド国家は、「共に歩む力」を持つ者が勝者となる。
そのとき、世界の人々が自然と集い、信頼し、協働したくなる国——それこそが次代のブランド国家である。その第一歩は、過去の栄光ではなく、未来に何を差し出すかを語ることから始まる。未来の国家ブランドとは、見せびらかす旗ではなく、手渡す地図である。日本はその地図を、世界の人々と共に描くことができる希少な存在となりうる。
- https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2023 ↩︎
- ジョセフ・サミュエル・ナイ・ジュニア(Joseph Samuel Nye Jr. )は、アメリカ合衆国の国際政治学者。980年代のアメリカ覇権衰退論に対し、ハード・パワー(典型的には軍事力や埋蔵資源など)ではなくソフト・パワー(政治力、文化的影響力など)という概念を用いて議論を行い、『文明の衝突』論を提示したサミュエル・P・ハンティントンや『大国の興亡』のポール・ケネディに対して批判的立場をとった。 ↩︎
- https://www.pewresearch.org/global/2024/06/11/is-u-s-democracy-a-good-example-to-follow/ ↩︎
- https://www.edelman.com/trust/2025/trust-barometer ↩︎
- https://www.jiia.or.jp/research-report/europe-fy2021-01.html ↩︎
- ユヴァル・ノア・ハラリ『21 Lessons for the 21st Century』(2018年) ↩︎
- Hannah Arendt, On Violence(『暴力について』), 1970年 ↩︎
- ニーアル・ファーガソン『文明:西洋が覇権をとれた6つの真因』(勁草書房) ↩︎