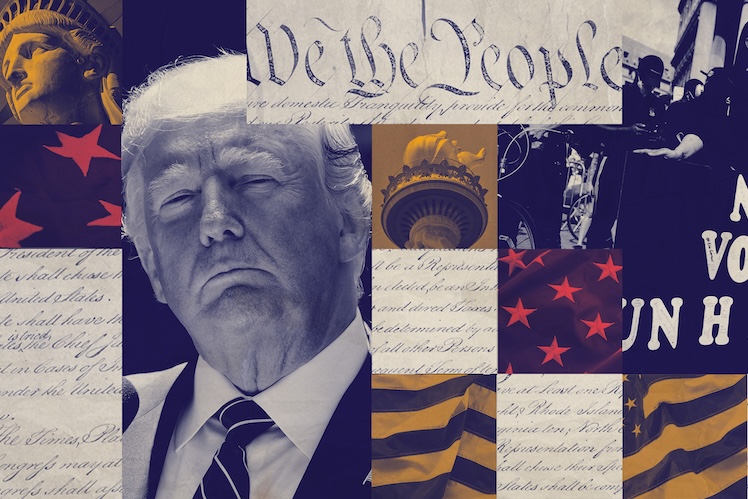
ブランドの「正義」は誰のためか? ~パーパスとポピュリズムの狭間で
Cover collage: ACLU(アメリカ自由人協会のサイトより1)
マーケティングやブランディングが、単なる売上のための道具ではなくなって久しい。かつてブランドは製品やサービスの品質保証であり、消費者に安心と利便性を提供する「中立的な消費の潤滑剤」として機能していた。しかし今、その「中立性」こそが虚構であり、時代遅れの発想となっている。企業とブランドは常に、どこかの価値観に加担しており、沈黙することすら政治的な選択なのだ。
リーマンショック以降の経済的利益追求資本主義の見直しやインパクト投資の勃興を経て、2010年代後半から2020年代前半にかけて急速に拡がった「ブランド・パーパス」時代は、企業が社会課題を積極的に語る時代として記憶されるだろう。多くのブランドが、サステナビリティ、多様性、公平性、インクルージョン(DEI)、LGBTQ+の権利、環境問題などをテーマに、「何を売るか」ではなく「何を信じているか」を発信し始めた。
中でも、先鋭的なブランドは価値観を具体的な行動で示し始めた。ナイキは人種差別への抗議の象徴となり2、パタゴニアは「この地球を守るために存在する」と宣言し自社株を全て新たに設立した環境団体に寄付、ユニリーバのヘルマンズは食品ロスとの闘いをブランドのアイデンティティとした。企業が「社会の変革を担う存在」として自らを位置づける新たな物語が形成されたのだ。そして多くの企業がその流れに追随して、自らの社会的価値を定義することとなった。
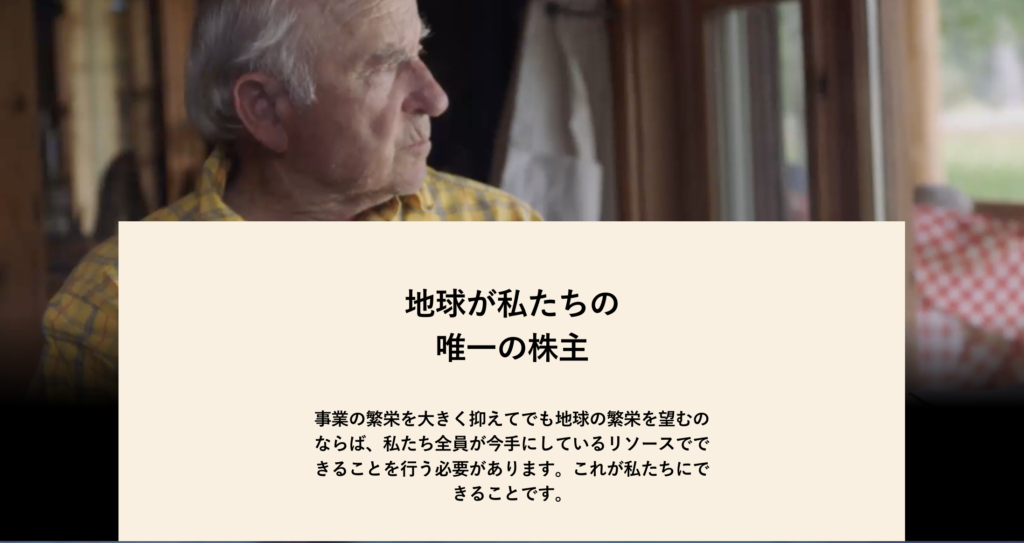
パタゴニアのウェブサイトより

ヘルマンズマヨネーズのウェブサイトより
だが今、その物語が転倒している。企業のパーパスが真の社会変革をもたらすどころか、表層的な倫理の演出にとどまり、かえって反動的な動きを助長してしまっているのではないかという問いが突きつけられている。社会的メッセージを掲げる一方で、企業は変わらず利潤追求を最優先し、部分最適で生活者の負担を強いるようなコスト転嫁を続けてきたところも多いからだ。環境に優しいとされる紙製バッグが高額で販売され、アップサイクルと謳われた品質の劣る「サステナブル」商品が消費者に押し付けられる。これは構造的な不公平を温存したまま、「正しい選択」をするよう誘導するマーケティングである。
保守的な運動は、このような企業の姿勢を「左傾化」と批判し、「ウォーク(Woke)」3という言葉を皮肉に使ってきた。企業の進歩的なメッセージは、いつしか反動勢力のターゲットとなり、政治的武器に転化されていった。本来、進歩的であるはずの立場が、商品化され、形骸化されたとき、それは新たな権威主義や排他主義を正当化する材料になってしまった。結果として、社会的正義を訴えてきたブランドが、皮肉にも保守的・排他的な運動の「敵役」として使われるようになってしまったのだ。
正義は売り物になるのか?
ブランドが掲げる社会的「正しさ」が、いつしか商品戦略と結びついたのは、必然でもある。購買行動は「善意の表明」としてマーケティングされ、エコな選択、フェアトレードな選択、多様性を祝福する選択が、消費者の“道徳的満足”を満たす手段となった。
この構造は、ある意味で心地よい。「正しいことをしたい」という人間の倫理感に寄り添い、それを手軽に実践できるかのように見せる。しかしその裏側では、グリーンウォッシュ的な環境アピール4、生活コストの上昇や、製品・サービスの品質の低下、情報の分断といった構造的な問題が放置されたまま、見えないところで消費者に転嫁されてきた。
企業イメージを高めるため、広告代理店に社会的なメッセージを訴求する広告を依頼しながら、企業としての活動はどこまで実態を伴っていたのか? 本当に中長期の構造変化につながる投資やビジネスモデル変革がなされていたのか? この問いに自信を持って明確に答えられる企業は、決して多くない。
トランプ政権とDEIの後退が示す「本音」
この表層性を露わにしたのが、米国における政治的な揺り戻しである。2025年、トランプが大統領に返り咲くと、連邦政府におけるDEIプログラムを即座に終了する大統領令が発令された。これに呼応するかのように、さまざまな大企業が社内のDEI関連部門や研修制度を削減・解体した。

たとえば、ウォルマートやボーイングはDEIへの取り組みを再検討し、SNSプラットフォーマーのメタ(旧フェイスブック)は社内DEIチームの縮小を実施した。Appleの株主総会では、DEIプログラムの継続を求める提案が可決され、逆風の中でも明確な姿勢を維持することが確認された。一方、TeslaはCEOイーロン・マスク氏の思想的影響もあり、DEIに対する表明を後退させ、関連する文言を年次報告書から削除するなど、真逆の方向性を示した。
これらの事例は、企業のDEIへの取り組みが政治的・文化的環境に左右されやすいことを示している。信念として根差していないブランド・パーパスは、逆風が吹いたとたんに撤退される「仮面」にすぎなかったという現実があらわになったのだ。
AppleとTesla——両極のブランド姿勢
AppleとTeslaの対比は象徴的である。Appleは、DEIとサステナビリティを企業戦略の中心に据えている。同社のメッセージでは、包括性と多様性の文化を育むことが強調されており、全従業員が最善の仕事を行える環境作りを目指している。 具体的な取り組みとして、歴史的黒人大学や先住民コミュニティへの支援、アクセシビリティ向上のための技術開発などが挙げられる。
2025年2月には、株主総会で保守的な投資家からのDEIプログラムを終了する提案が否決され、AppleのDEIへのコミットメントが再確認された。 このように、Appleは社会的責任とビジネスの成功を両立させる姿勢を明確に示している。
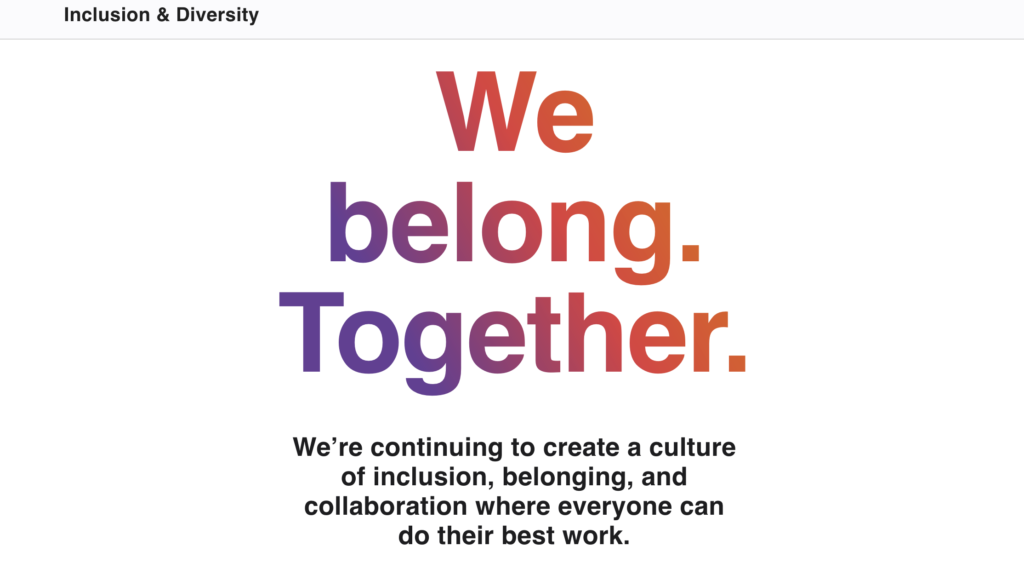
Appleのウェブサイトより。誰もがベストを尽くせるインクルージョン、帰属意識、コラボレーションの文化を創造し続けることを宣言
一方、Teslaは環境面でのインパクトこそ高いが、労働環境やガバナンス、多様性に関しては逆行する姿勢を見せている。2020年には初のDEIレポートを発表し、多様性と包括性を企業文化に組み込む意向を示していた。 しかしその後の数年間で、人種差別や労働環境に関する訴訟に直面し、2022年にはS&P 500 ESG指数から除外される事態となった。 CEOのイーロン・マスク氏は、DEIプログラムに対して批判的な立場を取っており、2024年には「DEIはただの逆差別だ」との発言をしているのは、象徴的なトップダウン型のブランディングの方針の変遷である。
この対比から学べるのは、社会的価値の実現がブランド組織の思想と一体であることの重要性だ。パーパスを掲げるだけでは足りず、それを事業戦略・組織文化・ガバナンスにまで浸透させているかどうかが、ブランドの真価を左右する。
ブランドは「自覚的」であれ
前提として確認したいのは、「ブランドが社会課題に取り組むことは、必須である」ということだ。むしろ、巨大な社会的影響力を持つ企業が、環境や人権、格差といった問題に無関心である方が、現代社会においては異常である。
「企業・ブランドは中立的であるべきだ」という考えはもはや通用しない。あらゆる発信、沈黙、表現、選択が政治的・社会的文脈に置かれてしまう時代において、ブランドは「自覚的」でなければならない。自社が何に価値を置き、誰と連帯し、何を犠牲にしているのか。そうした自問を避けずに向き合い、誠実に語るブランドだけが、次の時代の信頼を勝ち取ることができる。
消費者もまた、自らの眼差しを問い直す時
そしてこの時代、ブランドの姿勢を変える最大の力は、消費者にある。社会的課題に関心を持つ一方で、それを「ブランド任せ」にしてはならない。正しさは託すものではなく、共に担うものである。「この商品を買えば私は正義の側にいる」という幻想を脱しなければならない。革命はペプシでは起こらないのだ5。
すなわち消費は行動の一部にすぎない。発言、投票、教育、地域活動、社会的なコミュニティづくり—多様な方法で社会に関わることで、ブランドの外にある「公共性」を再構築することができる。ブランドの正義に安住せず、自らの意思で正義を組み立てることが求められているのだ。
ブランドにできるのは、社会運動の代行ではない。だが、それを補完し、ブランドの資産やリソースを活用して拡張することはできる。フィクションやスペクタクルを通じて「こうありたい未来」のイメージを提示し、人々の共感を喚起する。その影響力は、軽んじるべきではない。ただし、それには条件がある。偽善や演出ではなく、本質的な構造への理解と、自覚的な行動。そしてなにより、変化の当事者となる覚悟である。
ブランドとは誰のためにあるのか? それは、社会をより良くし、変えようとする意志を持つ者すべてのためである。その意志が揺るがない限り、ブランドの正義には意味がある。だが、ただのマーケティングで終わるなら、それは「正義を装った消費主義」にすぎない。ポスト・パーパスの時代に、ブランドと私たちは、その問いに正面から向き合わなければならない。
グローバルリーダーとしての日本企業の責任
最後に、トヨタやソニー、ユニクロといった世界的影響力を持つ日本発のグローバルブランドも、ますます「価値観の発信者」としての姿勢が問われるようになっている。日本企業には特有の慎重さと「沈黙による調和」があるが、今や沈黙は中立ではなく、立場の不在として批判される。たとえば、気候変動、ジェンダー平等、移民・多文化共生、人権といったテーマに対して、「何を語らないか」でも評価される時代なのだ。
ただし、大事なのは表層的な言葉を飾るより、行動で語ることだ。真のパーパスとは、耳障りのよいキャンペーンで“正しさ”を装うことではなく、“対話と変化”を続ける覚悟のことである。自覚を持って社会の構造に影響を与える長期的施策に注力する。そうした姿勢こそ信頼を生み、社会とともに歩むブランドの未来を示すものになるだろう。
「何を言うか」よりも「どのように存在し続けるか」で評価されること。一貫性を持って社会の構造に影響を与える長期的施策に注力する。こうした“静かなラディカリズム” を体現できるのは、日本企業に相応しい文化かもしれない。
- ACLU(アメリカ自由人協会):主に米国権利章典で保証されている言論の自由を守ることを目的とした、アメリカ合衆国のNGO団体。1920年設立。会員数は約500,000人。 ↩︎
- アメフト選手のコリン・キャパニック(Colin Kaepernick)は、人種差別に抗議するためNFLの試合で国歌斉唱中に起立することを拒否してひざまずき、トランプ米大統領ら保守派を中心に選手の処分を求める声によって解雇された。ナイキは、彼を“Just Do it”の30周年キャンペーン広告に起用したことで、人種差別問題や愛国心もからむ問題となってアメリカを分断する議論を呼んだ。 ↩︎
- 「woke」という用語は、アフリカ系アメリカ人のコミュニティで社会的不正義への意識を表現するために生まれたが、保守派または極右のフランスの政治家によって、反人種差別、フェミニスト、LGBT、環境運動に従事する個人を指す軽蔑的な意味で使われてきた。 ↩︎
- グリーンウォッシュ:環境に配慮しているように見せかける企業のマーケティング手法で、消費者を誤解させる行為 ↩︎
- 2017年のペプシの広告に起用されたケンダル・ジェンナーは、抗議運動を利益のために利用しているとして批判された。 ↩︎
























