
マーケティング・リブランドの失敗トップ10
裏目に出た10のリブランドとその理由
マーケティングのリブランドは、多くの場合、新たな読者、新たな関連性、新たな成長という「新しい章」の始まりを象徴する。しかし、最悪のリブランドは、長年築いてきたブランド・エクイティを「目新しさ」と引き換えにし、顧客のロイヤリティが後からついてくることを期待している。
慣れ親しんできたアイデンティティが突然消え、製品やサービスの中身が進化しないままでは、顧客は「進歩」ではなく「喪失」を感じる。以下の10の事例は、どれも教科書的な失敗例である。これらを検証することで、次のリブランドの危険信号を察知し、同じ轍を踏まない手がかりを得ることができる。
トロピカーナのパッケージ刷新(2009年)
トロピカーナは、棚の上でより高級感と新鮮さを感じさせる「モダンなデザイン」を狙ってパッケージを刷新した。従来の「ストローが刺さったオレンジ」のアイコンを排除し、ロゴタイプをソフトに、色味もシンプルな白基調に変更。しかしその結果、消費者はスーパーの棚で自分のいつものジュースを見つけられなくなった。ブランド認知の要であった視覚的手がかりが失われたのである。
売上は発売からわずか数週間で20%以上急落し、ブランドは即座に旧デザインへ戻す決断を迫られた。これは「見た目だけの進化」が顧客体験を破壊する典型であり、リブランドにおける認知資産の軽視がいかに致命的であるかを示した例である。
教訓:パッケージは棚におけるインターフェイスである。視覚的資産の一貫性は、味や品質と同じくらい重要である。
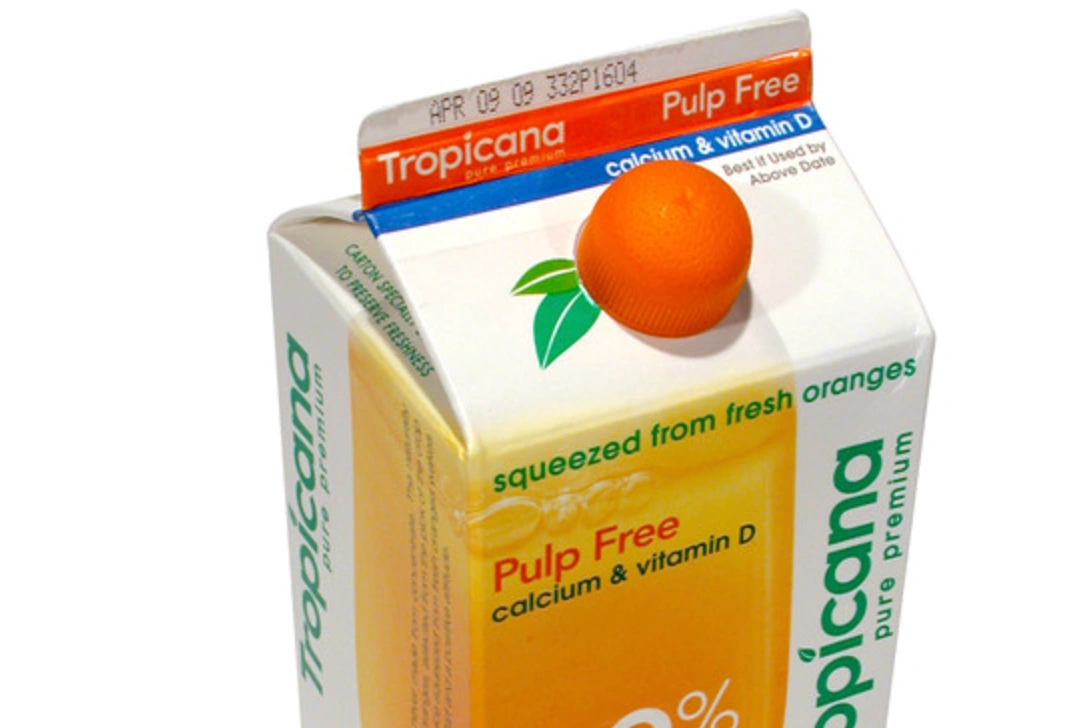
Gapの「一週間ロゴ」(2010年)
Gapは、より現代的でデジタルフレンドリーな印象を与えるために、新しいロゴを発表した。従来の青いボックスに白抜きの「GAP」というロゴから、薄いヘルベチカ体と小さな青い四角を添えた簡素なデザインへ。しかし、顧客はこの変更を「無意味なアイデンティティの放棄」と捉えた。
ファッション業界では、ロゴは「スタイルの象徴」である。だがGapは、素材・価格・ストーリーと結びつかない抽象的な変更を行ってしまった。オンラインでは批判が殺到し、わずか6日で旧ロゴに戻すという異例の展開となった。
教訓:見栄えの刷新は、製品価値やブランドの文脈とセットでなければならない。ロゴ単体では顧客の信頼を再構築できない。

ロイヤルメールの「コンシグニア」化(2002年)
英国の郵便事業を担うロイヤルメールは、通信・物流・電子商取引を包含する「未来志向のブランド」を目指し、「Consignia(コンシグニア)」という抽象的な社名へ変更した。だが、消費者や社員にとってこの名前は意味不明で、伝統ある「Royal」という国民的信頼の象徴を捨てたように映った。
メディアは「国家ブランドの放棄」と批判し、内部でも混乱が拡大。結局1年足らずで「Royal Mail」に戻す羽目になった。
教訓:業態の拡張を示したいときでも、既存の象徴的価値を捨ててはならない。伝統と変革のバランスがブランド継承の鍵である。

Netflixの「Qwikster」分離計画(2011年)
Netflixは、DVDレンタル部門とストリーミング部門を分離し、前者を「Qwikster」として独立させる戦略を発表した。狙いは業務効率化と料金体系の明確化だったが、顧客にとっては「二重ログイン」「二重請求」という手間の増加にほかならなかった。
SNSでは抗議が殺到し、CEOが謝罪文を発表。わずか数週間でQwikster計画は撤回された。
教訓:ブランド構造は企業の都合ではなく、顧客の利便性に基づいて設計すべきである。
ウェイト・ウォッチャーズから「WW」へ(2018年)
ダイエット支援から「ウェルネス」への拡張を狙い、「WW(Wellness that Works)」という新名称を導入した。しかしこの略称は、ブランドが長年培ってきた「減量成功」という明確な成果の印象を曖昧にした。
さらに時期を同じくして、医療用GLP-1薬による体重管理が急拡大し、WWの「ウェルネス」路線は焦点を失った。株価も下落し、ブランド認知の再構築に苦戦している。
教訓:ブランドの意味を広げたいなら、同時に「新しい提供価値」を明確に示す必要がある。

PwCコンサルティングの「Monday」化(2002年)
PwCから独立したコンサルティング会社は、親会社からの独立を象徴するために、一般名詞「Monday(マンデー)」を新社名として採用した。「仕事の始まり」を意味する軽快な語感を狙ったが、B2B市場では信頼性に欠けると受け止められた。
結局このブランドは市場に浸透する前にIBMに買収され、「Monday」は姿を消した。
教訓:企業ブランドでは、簡潔さよりも信頼性が優先される。抽象的なネーミングは戦略の代わりにはならない。

Uberの「ビットと原子」アイコン(2016年)
Uberは「テクノロジーと実世界の融合」を表す幾何学的な新アイコンを導入し、従来の「U」マークを廃止した。しかし乗客・ドライバー双方がアプリを見つけづらくなり、利用体験に支障をきたした。
「哲学的な抽象概念」は社内では美しく見えたかもしれないが、ユーザーにとっては単なる混乱だった。
数年後、Uberは再びシンプルで識別しやすいデザインへ戻している。
教訓:アプリアイコンは理念ではなくナビゲーションの道具である。

BPの「Beyond Petroleum」化(2000年代)
BPは「Beyond Petroleum(石油を超えて)」という新スローガンと共に、太陽のような花をモチーフにしたロゴを導入し、環境志向の企業像を打ち出した。しかし、2010年のメキシコ湾原油流出事故によって、そのメッセージは一瞬で信用を失った。
環境保護を掲げながら事故対応が不十分だったことが「グリーンウォッシング」の象徴とされ、BPは以後10年以上にわたって信頼回復に苦しむことになる。
教訓:語る前に行動を変えること。ストーリーは実践に裏打ちされなければ空虚である。

ラジオシャックの「The Shack」リブランド(2009年)
「The Shack」という略称で若年層にアピールしようとしたが、店舗体験や品揃えの刷新は伴わなかった。結果、既存顧客には違和感を与え、新規顧客の獲得にもつながらなかった。
SNSでは揶揄の対象となり、ブランドの老朽化イメージを払拭できないまま数年後に破綻へと至った。
教訓:名前だけ若返らせても、体験が古ければ顧客の心は動かない。

Twitterから「X」へ(2023年)
イーロン・マスクによる「すべてのアプリ」を目指す壮大な構想のもと、Twitterは象徴的な青い鳥と名称を捨て「X」へとリブランドした。しかし、世界的に認知されていた「ツイート」という文化的遺産を一夜にして消した結果、ユーザーは混乱と喪失感を抱いた。
プラットフォームとしての差別化要素も曖昧になり、広告主の信頼も低下。Xは依然として過渡期にあるが、ブランド資産を意図的にリセットするリスクを世界に示した事例となった。
教訓:象徴を捨てるなら、それ以上に強い「新しい物語」を提示しなければならない。
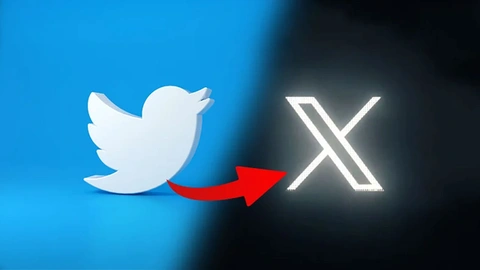
(出典:Brand Vision Insight他)
















