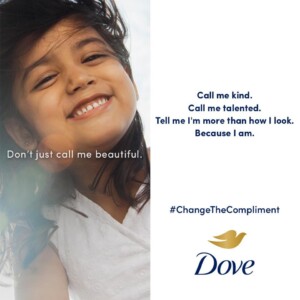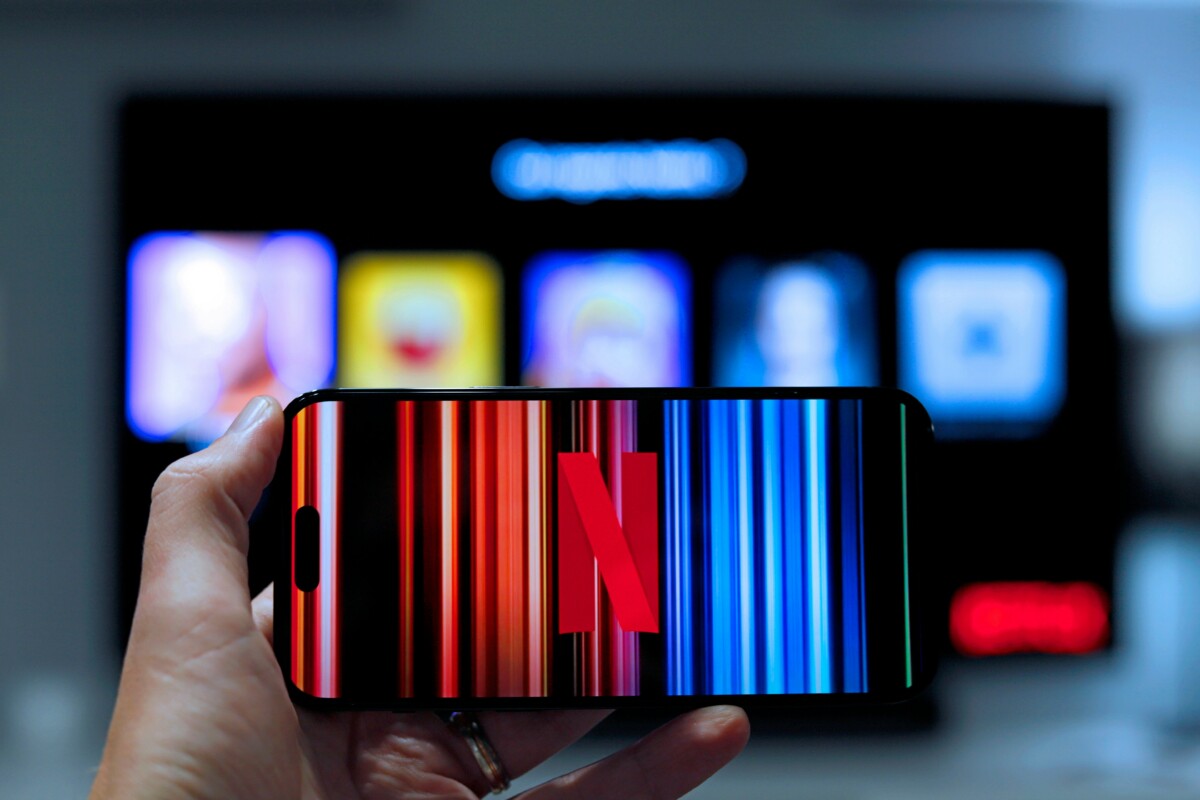
動画配信サービスは顧客ロイヤルティの限界に直面している― サブスク疲れと“乗り換え前提”のユーザー行動が加速
急増する「サブスクの乗り換え習慣」
英国では、動画配信サービス(SVOD)の契約と解約を短期間で繰り返す“サブスクリプション・サイクリング”が常態化しつつある。インサイト企業MTMとその調査ツール「ScreenThink」の最新調査によれば、すでに21%の消費者が配信サービスの乗り換えを実践しており、過去3年間でこの行動の発生率は4倍に膨らんだという。さらに42%が「乗り換えに前向き」と回答しており、ユーザーの間で“プラットフォーム固定”という概念は崩れつつある。
こうした状況は、ユーザーが「継続前提」で契約するのではなく、「見たい作品がある時だけ契約し、見終えたら解約する」という主体的な更新サイクルを選択していることを示している。
主な調査結果としては、英国オンライン人口の67%が少なくとも1つの有料配信サービスに加入しており、その半数以上が割引やバンドル経由での契約だ。だが、割引で加入した層は通常価格加入者よりも解約率が約2倍高く(73%対41%)、長期ロイヤルティの形成が難しいことが浮き彫りとなった。
Netflixの加入率は3年ぶりに減少し、76%から72%に低下。さらにパスワード共有率は6%から8%に上昇している。
なぜ「サイクリング」は業界にとって重大なのか
SVOD市場は成熟段階に入り、同じ視聴者層を巡る競争が激化している。各社は広告付きプランで低価格化を進めつつ、コンテンツ投資との両立に苦心している。
調査によると、Prime Video加入者の3人に1人が「Prime会員特典と切り離されるなら解約する」と回答しており、配信サービス単体では魅力が弱まる可能性を示唆している。さらに継続意向がある加入者のうち、40%が「支払っても月額5ポンド以下」と考えており、価格弾力性の限界が見えてきた。
MTMのフィリップ・エパイリ所長は、現状を「注目(Attention)経済から意図(Intention)経済への移行」と捉えている。つまり、視聴者の目を引くだけでは契約は維持できず、ユーザーの“意図”や動機に寄り添ったコンテンツ設計と体験が求められているという。
この背景から、Netflixがスポーツ中継に参入し、各社が動画ポッドキャストを新たな収益源として模索する動きが強まっている。
ロイヤルティが“貴重で最も脆い資産”になる時代
配信サービスの収益モデルにおいて、加入者のロイヤルティは最重要指標でありながら、その維持はかつてないほど困難になっている。
エパイリは「価格、パッケージング、UI/UXのすべてを抜本的に見直す必要がある」と提言する。特に、加入や解約がワンクリックで完了する現代において、プラットフォーム間の移動は摩擦が少なく、ユーザーが“契約しっぱなし”にしておく理由は失われつつある。
広告付きプランの普及による低価格化が進むほど、ユーザーは「複数サービスを同時に契約する」のではなく「必要なときだけ契約する」行動へ移りやすくなる。これは業界全体のARPU(ユーザー平均収益)に直接影響を与える。
データが示す未来とストリーミングの次の競争軸
調査結果によれば、ユーザーの自主的な判断による契約の出入りは今後さらに増える可能性が高い。サービス間の差別化が難しくなりつつあ今回の調査は、今後のストリーミング市場が「契約継続を前提としないユーザー」を基礎に組み立てられるべきであることを示唆している。差別化が難しい市場で、プラットフォームが勝ち残るための軸は、価格だけではなく、独自のコンテンツ戦略や、視聴体験そのものの品質へと移行していく。
つまり、オリジナル作品だけでなく、ライブ、スポーツ、動画ポッドキャストといった“代替不可能な視聴体験”がより重要な武器になる。また、推奨アルゴリズムの精度や広告インターフェースの洗練度といったUX領域も、ユーザーの“意図”をつなぎとめる決定要因となる。
エパイリは「加入者ロイヤルティこそが、今もっとも価値があり、同時にもっとも脆い資産になった」と述べており、動画配信サービスが向き合うべき現実を端的に表している。(出典:WARC, MTM)