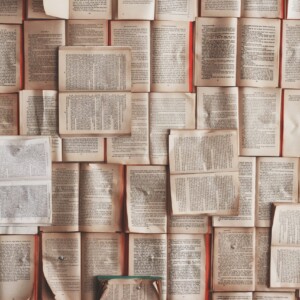都市の孤独を防ぐー〈つながりインフラ〉の最前線
都市は経済と情報の集積装置として発達してきたが、その光景は同時に個人にとっての「孤独の温床」でもあった。世界保健機関(WHO)は2025年6月の報告書で、世界人口の6人に1人が慢性的孤独を抱え、年間約87万人の早期死亡に結び付く1と指摘している。孤独は1時間当たり100人の命を蝕む計算だという。加えて米国公衆衛生総監報告書は、社会的断絶が「1日15本の喫煙」に匹敵する健康被害をもたらすと再確認した2。
つまり、孤独は喫煙や肥満に匹敵する健康リスクであり、都市の生産性やウェルビーイング、医療財政を蝕む“静かな公害”とも言える。孤独は都市生活の副作用であり、医療費や生産性損失を通じて社会全体が負担を余儀なくされているのだ。
かつて個人を支えてきた地域や家族、会社、学校などのコミュニティは、流動化・小規模化・高齢化によって結合力を弱め、都市は高密度でありながら関係が希薄な〈孤独インフラ〉と化した。現代都市は依然、交通効率や床面積利益率を絶対指標として設計され、人間関係を醸成する余白を切り詰めてきたからだ。
高層オフィス街は夜ごと無人化し、駅前広場は歩行速度を最優先する動線によって長時間の滞在を暗に禁じる。都市を流れる人の群れは互いを観測しつつも、関係を結ぶ機会を奪われている。この物理的・制度的布置こそが、孤独を副産物として量産する都市の〈孤独インフラ〉にほかならない。
「おひとり様」社会の最大ボリューム化
日本でも「おひとり様」という言葉は、2000年代にポジティブな自己肯定のスローガンとして登場した。当時は一人焼肉や一人旅に挑む姿がメディアをにぎわせ、“自由を楽しむライフスタイル”の象徴として語られた。しかし2020年代後半、日本社会は〈おひとり様の常態化〉という質的転換点を迎えている。おひとり様の時代は、個を尊重する市場と、孤独を底上げするリスクが同時進行で拡大している。
2050年、日本の総世帯数に占める単身世帯の割合は44.3%に達し、東京圏では52%を超えると推計される。50歳時点未婚率は男性33%、女性20%になる見込みだ3。平均寿命の延伸により「結婚も同居家族もいないまま老いを迎える」というライフコースが多数派になる。結婚・出産という人生イベントが選択肢の一つに過ぎなくなり、家族のいないまま老いを迎える人が最大のボリューム層へ変化する。
この構造変化は社会の基幹システム―住宅政策、税制、医療・介護、交通などを家族単位から個人単位へ再構築することを迫る。同時に、単身向け外食、ソロ旅行、推し活、終活サービスなど「おひとり様市場」が推計27兆円規模へ膨張し、企業は新たな需要を掘り起こしている4。自由の拡大と孤立リスクが表裏一体で進むこの時代を、私たちはどう生き抜くか。
孤独の社会問題化と対策法整備
日本でも2000年代から高齢単身世帯の増加と若年層の引きこもりが並行し、社会的孤立は潜在課題として指摘されていた。内閣府が2023 年3月に公表した全国調査では、15〜64 歳の「広義の引きこもり」は約146万人に達するという5。しかし具体的な省庁横断政策は存在しなかった。その転機となったのは 2020年の新型コロナウイルス感染拡大 である。外出自粛とリモート生活の長期化が孤立感を顕在化させ、自殺者数(特に女性・若年層)が 11 年ぶりに増加へ転じた。国民の不安が高まる中、当時の菅義偉政権は英国を参考に「孤独担当大臣」創設を検討し始めた。
内閣府が2024年に公表した「孤独・孤立実態調査」では、孤独を感じる層が4割に達している。注目すべきは孤独感が高い年代が若年層と中高年の双方にまたがる点で、未婚・既婚の別を問わず「つながりの希薄化」が広範に進行している事実を示す。こうした経緯で、2024年に施行された「孤独・孤立対策推進法」6により、国と自治体が対策を講じる枠組みが整った。しかし課題は制度の存在ではなく、孤独を予防する場と仕組みをどう実装するかにある。
制度だけで孤立が解消しない理由は2つある。第1に、孤立の発生が年齢・経済状態・ジェンダー・仕事や家族関係など複数要因の重層交差で決まるため、縦割り施策では対応しきれないこと。第2に、孤立を可視化する指標が依然として「相談件数」「自殺率」などネガティブなアウトカム中心で、日常的ウェルビーイングの把握や予防指標が整備されていないことである。

孤独感が発生する心理メカニズム
NHK ドラマにもなった話題の漫画『ひとりでしにたい』7では、都会のワンルームで孤独を抱える主人公が、ふとしたきっかけで「だれかとつながること」を選び直すまでを描いた。物語が示すのは、孤独が単なる感情ではなく、〈私は歓迎されていない〉という思い込みとそれを強化する生活構造の問題だという点だ。
この“内側の歪み”を手当てしないかぎり、どれほど交流の場を増やしても心は晴れない。重要なのは、孤独感の起点が「人が足りないこと」そのものではなく、「自分は歓迎されていない」という考えのクセだという点だ。心理学ではこれを“拒絶感受性”と呼ぶ。
孤独感は、既読スルーや誘いを断られた場面で「嫌われた」と即断する“拒絶感受性”が呼び水になる。コンビニやコールセンターで怒号を飛ばす、店員に延々と説教する―こうした高齢クレーマーは業界では〈カスタマーハラスメント〉と呼ばれ、団塊世代が退職した2000年代後半から増加が指摘されてきた。関西大学社会学部の池内裕美教授は、これらを「退職などで失われつつある自己有用感(存在意義)が、過去の栄光や知識を誇示したい欲求と結び付き、歪んだ承認欲求となって従業員への過剰な要求として噴出する」と指摘している。
こうした孤独対策における心理学的なアプローチの研究が進んでいる。エビデンスが厚いのが、認知を修正する手法である認知行動療法(CBT)だ8。これは瞬発的な思い込みを紙に書き出し、事実に照らして検証し、より現実的な見方に置き換え、最後に小さな行動で確かめるという四段階を反復させる。
また、拒絶感受性の燃料になるのは「自分には価値がない」という自己批判である。最近注目されるセルフ・コンパッションは、その批判に「友人にかける優しい言葉」を重ねる技法だ。友人が落ち込んでいるときにかける励ましの言葉を、そのまま自分に向けて語るわけだ。
そして孤独は個人の認知を整え、テクノロジーで隙間を埋めても、行動を起こさなければ解消しない。そこで生きるのがピアサポート(様々な経験を持つ人々が、互いに支え合う活動)と社会的処方(Social Prescription:医療や福祉機関が、薬や治療だけでなく、地域活動や趣味グループ、ボランティア活動などを紹介することで、人々のwell-beingを高めようとする取り組み)である。
そして近年、こうした都市の孤独を埋める“第三の共同体”が世界各地で芽吹きつつある。コリビングやコミュニティ・カフェ、時間の交換経済、ベンチ型カウンセリングなどだ。それらはサービスであると同時に、心のウェルビーイングを支える新たな社会インフラである。なぜそれらが次世代インフラになり得るのかを考察していこう。
「マインド・コンビニエンスストア」─ソウル発、“孤独の入口”を塞ぐ心理的サードプレイス
単身世帯比率が40%近い韓国・ソウル市は2025年、「Seoul without loneliness」を掲げ、5年間で約451億ウォン(約47億円)を投じる包括プランを始動した。その象徴が、市内各所に開設された「マインド・コンビニエンスストア」である9。
ここではマッサージチェアやフットスパ、インスタント麺コーナーといった“ゆるい共有体験”を提供しつつ、常駐カウンセラーが心理相談に応じる。利用者は商品を買うのと同じ気軽さで心のケアにアクセスでき、開設後まもなく24時間ホットラインの年間目標件数を上回る相談が寄せられたという。

ソウル・メウム・コンビニエンスストア(ソウル特別市)のセルフサービスステーション。このスペースは、訪問者がプレッシャーの少ない居心地の良い環境で、無料で食事をしたり、メンタルヘルスサポートを利用したりすることを可能にしている。
行政が従来型福祉では拾いきれない「予備軍段階の孤独」を捕捉し、福祉を日常消費の文脈に接続し、孤独の予備軍を“入口”で拾うこのモデルは、商業とケアのハイブリッドとして注目される。
コリビングの進化─“住まい”を介した他者との長期的関係構築
都市における孤立は居住形態とも深く結び付く。ベルギー発のコリビング企業Cohabsは2025年に米ワシントンD.C.で6棟の集合住宅を買収し、入居者最大35人がキッチンやシアタールームを共有する大規模ハウスを展開した10。
入居者同士の共同食事、地域ボランティア、週次“家族会議”を組み込み、「ルームシェア以上、家族未満」の長期的な関係をデザインしている。同社は賃貸契約の硬直性を緩め、コミュニティ運営をサブスクリプション化したことで、単身者でも安定した“ご近所付き合い”が可能となった。住まいは単なる居住空間ではなく、人間関係を媒介するプラットフォームへと転換されつつある。

ベルギー発のコリビング企業CohabのColiving
また、フランスのCommuneは2024年2月、シングルペアレント専用のコリビング施設をパリ郊外に開業した。13戸の個室に共有キッチン、キッズルーム、相互託児アプリを備え、「子育てと孤立」を同時に解く仕組みとして注目されている。いずれも賃貸モデルの制約を超え、住まいをプラットフォームに変えることで“同居者コミュニティ”を半永続的に維持する試みだ11。
公共空間を再編集する都市政策─バルセロナのスーパーブロックと英国「チャッティ・ベンチ」
屋外空間自体を“つながり装置”に変える都市もある。バルセロナは2016年から車道を減らして歩行者優先の「スーパーブロック」を整備した。クルマ中心のインフラを転換し、人が滞留し語らう微地形を増やすことで、単なる交通政策を越えた公衆衛生効果を生み出している12。

バルセロナのスーパーブロック。交通エリアを住民の遊び場に転換し、緑地を提供し、住民のための座席を設置している。住民の平均寿命は約200日延びたという(バルセロナ保健機関BCN ecologia調査)
一方、英国各地で広がる「チャッティ・ベンチ」は既存のベンチに“Sit here if you don’t mind someone stopping to say hello”という看板を設置するだけの低コスト施策だ。介護大手Anchorが支援する取り組みでは2024年までに200基を超え、地元自治体や慈善団体が波及させている。都市の隙間に「話しかけてもいい」という合意を可視化し、偶発的な対話のハードルを劇的に下げた13。

英介護大手のAnchorが支援するChatty Benches(おしゃべりベンチ)
スコットランド・グラスゴーでは、女性限定の 「Pal Project」 が月1回の緩やかなイベントを開催し、約5万人の母体コミュニティが孤独に悩む若年女性をリアル空間へ誘導する。参加者は趣味ワークショップや散歩会で関係を築き、若手起業家向けの「Glow Business Members Club」も併設されている。同性・同世代という安全圏を設計し、職業やライフステージの差を超えた相互扶助を可能にした。ジェンダー特化コミュニティで、若年女性の“縦横の連帯”を支える狙いだ14。
コミュニティ・カフェとケアビジネス─日本における地域密着型モデル
独身者が5割、高齢者が4割を超える―2030年代の日本社会では「ひとりで老いる」ことがごく普通になる。その副作用として進む孤独・孤立をどう減らすか。鍵は家族とは別の“ゆるいネットワーク”を張り巡らせることにある。
若手~中年向けのソーシャルアパートメントが都内で入居率100%を記録し、リビングやワークラウンジで緩い交流が生まれている。家を「閉じた城」から「半公共空間」へ翻訳し直す動きが、世代を超えて加速している15。
退職後の男性が集うメンズ・シェッド(直訳すると「男性たちの小屋」)は、木工や修理を口実におしゃべりできる“小屋”。 日本で初めて北海道でNPOが立ち上げた16。一方、東京では女性キャリアカフェ「シャベリバ」が定期開催され、仕事や生き方を語れる横のつながりを提供している。家族や会社に代わり「同性・同世代」のゆるい共助回路が立ち上がりつつある。

メンタルヘルスを支える“ベンチ・セラピー”─ジンバブエ発「フレンドシップ・ベンチ」の国際展開
医療資源の乏しい国で始まった草の根支援もグローバルに広がる。ジンバブエの精神科医ディクソン・チバンダが考案した「フレンドシップ・ベンチ」は、地域の高齢者を2週間研修し、公園や図書館に置かれたベンチで傾聴セッションを行う仕組みだ。2025年4月、英国サセックスでパイロットが開始され、6〜8週間の面談で8割が寛解を維持したと伝えられる17。専門家不足を補い、文化的背景が異なる国でもスケールできるシンプルさは、孤独対策の“フラットパッケージ化”を示唆する。
〈つながりインフラ〉が描く未来図
いずれも共通しているのは、孤独を「医療」「福祉」の周辺課題に留めず、居住・商業・公共空間・デジタルプラットフォームにまたがる“基盤インフラ”と捉え直している点である。空間の所有を共用へ、さらに共同管理へとフェーズアップし、住民が“場の編集者”になる仕組みを用意している。空間を共につくり、共に営む行為自体が“関係のトレーニング・ジム”となり、人々の社会的筋力を鍛える。これこそ孤独インフラを共創インフラへ書き換える実践的ロジックだ。
形態もアクターも異なるが、「空間」「時間」「行為」という三つの共有資源を媒介に、“ゆるく持続する関係”を仕組み化している。従来のコミュニティは会社、学校、家族といった閉じた制度内に存在し、人生段階が変わるたびに断絶を生んできた。新しいコミュニティは制度外部で横断的に接続し、居住や購買、ボランティアといった日常行為と不可分に絡め取ることで、「関係性を使い捨てにしない都市」を構築しようとしている。
行政が資本投下しやすいハード整備と、ビジネスが収益化しやすいサービス設計が重層的に組み合わされ、単体では持続しにくい“つながり事業”をエコシステム化している。都市は従来、「速度と密度」を競争力としたが、ポスト・パンデミックの観点からは「交流と相互扶助」が新たな競争力へ転じる。ある意味で都市は、経済インフラから〈共創インフラ〉へアップグレードを迫られていると言える。
孤独は都市が抱える“静かな公害”だが、逆手に取れば多様な事業機会を生む“関係産業”の母胎にもなる。今、世界各地で芽吹くコミュニティとビジネスは、都市を再び人間のサイズに合わせ、心のウェルビーイングを核心に据えた新しい経済圏を形づくりつつある。
そして、都市の孤独を防ぐ新インフラとは、鉄道や上下水のように目に見えるパイプではなく、人と人を結び直す“関係のパイプ”である。その構築はコストではなく投資であり、心のウェルビーイングが新たな都市競争力となる時代、これらのコミュニティは社会の基盤機能へ昇格していくに違いない。
孤独を防ぐテクノロジーと経済システム
孤独の問題を解消するために、公園やカフェなど“居場所”づくりは欠かせないが、空間を整えるだけでは限界がある。そこで近年は、AIやロボット、時間通貨、医療制度といった〈場の外側〉の仕組みを使い、日常に縫い込まれた孤立を根底から和らげようとする試みが世界各地で加速している。
AIコンパニオン─「いつでも応答してくれる友人」が雲の上にいる安心感
卓上型ロボット ElliQ は、高齢者に雑談をふり、服薬を促し、家族とのビデオ通話も取り次ぐ“対話特化エージェント”だ。Intuition Roboticsによると累計15万台を販売し、利用者の82%が孤独軽減したという18。若年層ではチャット型人格AIのReplika や Character.AI が人気を集め、米国の家庭向け調査で「AIとの会話が心の支えになっている」と答えるZ世代は多数派に達している。24時間反応してくれる“第三の友人”がクラウド側に常駐することが、リアルな人間関係の摩擦と時間制約を補完しつつ、孤独の予防線を張る。

分身ロボットとテレプレゼンス─身体制約を越えて“そこに居る”を実装する
身体が動かなくても社会とつながれる―そんな願いを形にしたのが、日本の分身ロボット OriHime だ。開発元のオリィ研究所は「人類から“孤独”をなくす」を掲げ、遠隔操作で首と腕を動かし、カメラとスピーカーを通じて会話できる小型機を2014年に発表した。その後大型モデル OriHime‑Dが登場し、リモートワーカーや重度障害者が接客や案内業務をこなせるよう改良された 。

東京・日本橋に2021年開業した 「Avatar Robot Café DAWN」
象徴的な舞台が、東京・日本橋に2021年開業した 「分身ロボットカフェDAWN ver.β」 である。店内を動き回るOriHime‑Dは、在宅の「パイロット」がパソコンや視線入力で操作し、客と会話しながらドリンクを運ぶ。出勤が困難なALS患者や育児中の主婦が“分身”を通じて働くこのカフェは、2年で延べ100人以上の就労機会を生み、「働く場を失った人を社会の接点に引き戻す」モデルとして国内外から注目を浴びた 。2025年4月にはデンマークに海外1号店が半年間の実証を開始し、遠隔就労と英語対応の仕組みがグローバルに展開されている19。
分身ロボットは単なるガジェットではなく、「遠隔から他者と役割を共有する」という新しい社会参加の形を都市設備として組み込もうとしている。
時間通貨─数字で可視化する“助け合いの循環”
お金ではなく「1時間」を単位に人の行為を交換する タイムバンク は、コミュニティの“弱い紐帯”を数値化して孤独を減らす。英国 TimeBanking UK は350以上の地域バンクを束ね、参加者の孤独感の改善を図っている20。
米ニューヨークのNPOは買い物代行やガーデニングの依頼を1時間=1クレジットでマッチングし、開始半年で1万8,000時間が流通。AIが移動距離・スキル・過去の評価を学習し、最適なマッチを推薦することで、頼む側の申し訳なさと頼まれる側の負担感を同時に軽減する仕組みが完成しつつある。経済力や年齢差を超え、水平な関係性が“取引データ”として蓄積される点が、タイムバンクを社会インフラへ近づけている。

医療が“関係”を処方する─ソーシャル・プレスクライビングの進化
英国NHSは薬ではなく社会活動を紹介する ソーシャル・プレスクライビング を拡大し、リンクワーカーは全国で3,500人を超えた。最新の試行では、孤独リスクの高い患者にサッカー観戦を“処方”し、参加者の8割が自主的に継続的な地域活動に関わることを目標としている21。背後では電子カルテを解析するAIが生活背景と孤立リスクを予測し、最適な地域活動をデジタル処方箋として出力する仕組みが開発中だ。医療が「治療」だけでなく「関係資本の生成」に保険財源を投じる―そんなパラダイムシフトが現実味を帯びてきた。
個人としての孤独社会への戦略とは?
最後に、社会インフラだけでなく、現代を生きる個人としての孤独社会への戦略を考え実行していくことを考えてみよう。家族・会社・学校の結合力が弱まる未来に備え、私たちは「ゆるい糸を何本も持つ」ことが必要だ。
たとえば男女のつながりも、結婚に偏ると、未婚・非婚層ほど交流回路を失いやすい。高度成長期の日本は、恋愛と結婚を一直線に結び付けるモデルを教科書にしてきた。しかし未婚率が上昇し、カップルの解消や死別も増える21世紀には、情緒的な支えを1対1の専売特許に委ねるのは極めてリスキーになる。そんな中で、 婚活を超えた“男女ゆるネットワークが新たな時代の潮流になりつつある。
マッチングアプリの統計では「友活」「飲み仲間」タグの登録増加率が恋愛タグを上回り、利用動機の多様化が顕著だ。累計会員 19万人の1対1の相席ラウンジ「THE SINGLE」でも、来店理由の約半数が「まずは友人をつくりたい」と恋愛・結婚より“ゆるい付き合い”を目的に来店する層が半数を超えるという22。シニア層でも同様の動きがある。登録 12 万人の50 代以上限定の友活アプリ「R50Time」23の開発会社アンケートでは「配偶者とは別の世代横断コミュニティが欲しい」と答えた利用者が 68%に達し、“再婚”より“再友達”志向の高さを示した。
人間だけではなく、ペットとしての動物も孤独感を防ぎ、情緒的コミュニケーションを担う重要な存在になった。国内ペット市場は成長を続け、高齢・単身世帯の増加で“伴侶”としての需要が高まり、孤独感を緩和する社会的クッションの役割も強まっている。都市部単身世帯のペット飼育率は26%に上り、散歩や通院を通じて人間同士の弱い紐帯を生む機会ともなっている。
社会はすでに一対一の濃い絆より、複数のコミュニティの浅い糸を束ねる網状モデルへ移行している。恋愛・友情・共感のチャンネルを複数保持すること。漫画「ひとりでしにたい」の主人公が学んだように、完璧な相手を一人見つけるのではなく、細い糸を複数編んでおくことこそが孤独社会をしなやかに生き抜く鍵になる。
ここで重要なのは、同じ世代や属性で固まるのではなく、異なる世代や職業、性別など多様性を持ったコミュニティを意識的に形成し、関わっていくことだ。同質な仲間だけで固まる「閉じた結束」は安心感をくれる一方、情報や視野を狭め、孤立を深める温床にもなる。参加メンバーの世代・性別・職業が多様なサークルに属する高齢者ほど、要介護認定を受ける確率が最大24%下がるとの追跡調査が報告されている24。
つまり「異質な誰か」との弱い紐帯は、心身のレジリエンスと社会的信頼を同時に底上げする“橋渡しの資本”だ。世代や属性を意識的に混ぜたコミュニティは、新しい役割や学びを生み、孤独や偏見を中和する循環ポンプになる。単身・高齢化が進む日本でこそ、多様なメンバーシップを重ね持つことが、個々のウェルビーイングと社会全体の結束を支える最小にして最強の戦略と言える。
結局、私たち全員が「誰かの確かな糸」にはなり得ない。だからこそ細くても多彩な糸を編み重ね、互いをそっと支え合う網を広げておく。その網が日々の好奇心を運び、偶然の出会いを結び、いざ孤独が忍び寄った時には柔らかい着地点となる。孤立を恐れて縮こまるのでなく、小さな一歩で異質な誰かと視線を交わす―それこそが〈おひとり様時代〉をしなやかに愉しむ、最も賢いセルフ・セーフティネットかもしれない。
<脚注>
- WHO 社会的つながりに関する委員会 報告書(2025):https://www.who.int/news/item/30-06-2025-social-connection-linked-to-improved-heath-and-reduced-risk-of-early-death?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- 米国公衆衛生総監報告書:https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-social-connection-advisory.pdf?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- 国立社会保障・人口問題研究所の推計:https://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2024/hprj2024_gaiyo_20240412.pdf ↩︎
- 矢野経済研究所 『2019 おひとりさま市場総覧』他 ↩︎
- 内閣府 「令和4年度 我が国におけるひきこもりに関する実態調査結果」(2023-03-31公表) ↩︎
- 孤独・孤立対策推進法 内閣府: https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhou.html ↩︎
- https://www.nhk.jp/p/hitorideshinitai/ts/M6X7266P6P/ ↩︎
- 国立精神・神経医療研究センター:https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/rinshoshinri/rinshoshinri_blog20220713.html ↩︎
- The Guardian・Business Insider:https://www.businessinsider.com/experts-say-seoul-322-million-plan-fight-loneliness-not-work-2024-11?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- Cohabs:https://cohabs.com/、https://www.washingtonian.com/2024/12/23/cohabs-and-the-resurgence-of-co-living-in-dc/?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- Commune:https://commune.house/en/home/ ↩︎
- バルセロナのスーパーブロック:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935124004547?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- Anchor チャッティベンチ:https://www.anchor.org.uk/media/campaigns/chatty-benches?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- Pal Project:https://www.thescottishsun.co.uk/fabulous/14969595/friends-women-lonely-glasgow-girls-club/?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- ソーシャルアパートメント:https://www.social-apartment.com/lifestyle/detail/20250314114512?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- メンズシェッド:https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1038714/?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- フレンドシップベンチ:https://www.theguardian.com/society/2025/apr/08/friendship-benches-mental-health-support-sussex?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- 卓上ロボットElliQ:https://elliq.com/?srsltid=AfmBOoro-cRiymHVd3VZAHBKSNIswtAankarwfXjyTR8Cs8vpmiAkHdY ↩︎
- 分身ロボットカフェDAWN ver.β:https://ledge.ai/articles/orihime_social_inclusion_denmark ↩︎
- TimeBanking UK:https://timebanking.org/wp-content/uploads/2024/11/SUMMARY-WORLD-REPORT-2024.pdf?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- ソーシャル・プレスクライビング:https://www.the-independent.com/bulletin/news/depression-treatment-gp-football-tickets-b2792665.html?utm_source=chatgpt.com ↩︎
- The Single:https://single-aiseki.com/ ↩︎
- R50Time:https://r50time.jp/ ↩︎
- 日本老年学的評価研究(JAGES)による6年間の縦断調査(対象6万1,281人,65歳以上) ↩︎