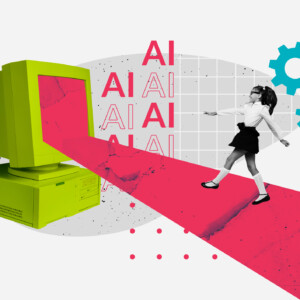BMWが感情に訴えるブランディングで成功を導く方法—EV時代における「走る喜び」の再構築
感情を設計するブランドとしてのBMW
BMWは、単に「速いクルマ」を売るブランドではない。長年一貫して売ってきたのは、馬力ではなく「気分」や「物語」であり、自分はどんな人間でありたいかというアイデンティティそのものだと言ってよい。BMWに乗るとは、機械に乗り込むというより、自分の理想像を身にまとう行為に近い。
クラシックなプロポーションのクーペから最新のEVまで、このブランドのプロダクトは、性能スペック以上に「雰囲気」を設計してきた。その積み重ねの結果、BMWは高級車メーカーの多くが目指しながらも維持しきれない領域——クルマが単なる移動手段ではなく、憧れや所属感、「走る喜び」といった抽象的な価値を体現するブランド世界——を確立している。
最近のホリデーシーズンでも、その姿勢はむしろ強まっている。静かなモーターと巨大なタッチスクリーンが当たり前になった今、BMWはEV BMW iX3 のキャンペーンで「自動車そのものではなく、感じ方をつくっている」というメッセージを打ち出した。アルゴリズムとソフトウェアが支配するモビリティの未来に、人間らしい感覚を取り戻そうとする宣言であり、「究極のドライビングマシン」がただのスマートガジェットに矮小化されることへの抵抗でもある。

デザインとストーリーテリングがつくる情動の世界
もっとも、感情に訴えるストーリーテリングは、ここ数年で突然始まったものではない。テック企業とラグジュアリーの競争が激化するずっと以前から、BMWは“Freude am Fahren(走る喜び)”を掲げてきた。1970年代の「究極のドライビングマシン」というコピーも、表向きは性能を語りながら、その裏側では「路面の感覚を楽しめる熟練したドライバーでありたい」という自己イメージに訴えかけるメッセージだったと言える。
しかし、その物語の構造は時代とともに変化している。近年のBMWのマーケティングは、「ドライバー=ヒーロー」という直球の構図から、「ライフスタイルや感情全体をデザインする」方向へと、意図的にトーンを柔らかくずらしてきた。トルクや出力だけでなく、自由、自己実現、成功といった感覚そのものをパッケージ化し、映画のような短編映像や没入型ショールーム体験など、あらゆるタッチポイントで「所有することが一つの人生体験である」と感じさせる設計に振っている。
これは感情的ブランディングの王道であり、人間の欲望や不安、理想像に働きかけるアプローチである。顧客が買うのはスペックではなく、「このプロダクトを持つとこう感じられるはずだ」という期待だ、という前提に立っている。BMWはその前提を徹底し、デザイン言語から販売空間の演出に至るまで、ブランドに触れる体験のすべてを感情のトリガーとして扱っている。
ただし、そこには大きな矛盾も潜む。EVが静かになり、デジタル化が進み、プラットフォームやパーツが共通化されるなかで、ブランドはどこまで「感情」を差別化要素として維持できるのか。直列6気筒エンジンの生々しいサウンドが、ソフトウェアで調整された疑似音に置き換わったとき、「走る喜び」は同じ強度で成立するのか。この問いこそが、BMWが現在進行形で向き合っている課題である。

感情を前提にしたプロダクトデザイン
BMWの新型車は、そのたびに熱狂か激論、あるいはその両方を生むようにデザインされている。立体的なボディラインからドライバーを包み込むコクピットの構成まで、ディテールはすべて「感情の引き金」として設計されている。顧客が求めているのは移動能力以上のものであり、自信や誇り、少し大げさに言えば「舞台に立つような高揚感」だ、という前提に立つからこそ可能な設計思想である。
ここ数年、賛否を大きく分けた巨大なキドニーグリルも、この文脈で理解できる。ブランドの象徴をあえて誇張したその造形は、「やり過ぎ」という批判と同じくらい強い支持も集めた。BMWが選んだのは、無難なデザインで誰の感情も動かさないことではなく、たとえ賛否が割れても「何かを感じさせる」選択である。普遍的な好感度よりも、強い印象と語りたくなる話題性を優先する価値観がそこにはある。

ハードウェアだけでは伝えきれない部分は、物語が補う。電気自動車i4のキャンペーン「父と息子。喜びは永遠に」では、父から息子へ運転の楽しさが受け継がれていく姿を描き、走ることが家族の記憶や自由の象徴になり得ることを示した。最近のホリデーフィルムでは、子どもと祖母がBMWを通して再びつながる様子を見せ、バッテリー残量やタッチスクリーンに神経をすり減らす時代になっても、「クルマでどこかへ向かうこと」が世代を超えた喜びになり得ると訴えかける。
このようなアプローチは、感情の面では強く作用する。一方で、ある種の賭けでもある。なぜならBMWが売ろうとしている「喜び」は、現実の運転環境——都市部の渋滞、監視カメラ、支援システムの増加、保険料の高騰——によって、かつてないほど損なわれやすいものだからだ。ブランドは本質的に、現実が提供しづらくなった感覚を、なおも約束し続けていることになる。
デザイナーとブランドが学べること
デザイナーやブランドストラテジストの視点から見れば、BMWのケースは一つの教科書になりうる。まず、機能的・技術的水準で信頼に足るプロダクトをつくる。そのうえで、それが人間の感情や自己像とどのようにつながるのかを物語として構築し、体験全体をデザインする——という二段構えである。
ただし、このモデルには重要な前提がある。感情に訴えるブランディングが機能するのは、その感情が実際の体験によって裏打ちされている場合に限られる、という点だ。BMWは長年培ってきたエンジニアリングの信頼があるからこそ「喜び」を語る余地を持てるが、その余地は無限ではない。
プロダクトの中身が平均化し、テクノロジー面での優位性が薄れれば、「感情」は単なる装飾として露出するリスクが高まる。特にEVへの移行は、機械的な個性の差を縮めてしまう側面があり、感情の約束と現実の体験の間にギャップが生まれやすい状況をつくっている。
その意味で、現在のBMWの戦略は、方向転換というより「再調整」と捉えるべきだろう。パワートレインが変わっても、約束する価値は変えない——未来のクルマが静かでソフトウェア駆動になっても、運転する感覚は人間的で豊かなものであり得る、と言い続ける姿勢である。
消費者がその約束をどこまで信じるかは、これからのプロダクトと体験次第だ。少なくとも現時点で言えるのは、BMWが「馬力」ではなく「感情」を競争軸に選び続けているという事実であり、その選択はEV時代のブランド戦争において、他社と大きく異なる勝負の仕方をしている、ということである。(出典・画像:BMW、Creative Bloq)